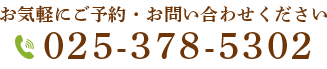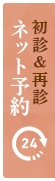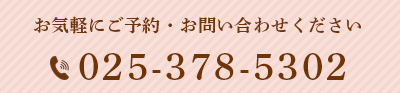審美歯科治療は、歯の美しさに焦点を当てた治療であり、代表的なものにはホワイトニングやクリーニングが挙げられます。
また、これらの治療の細かい治療内容、仕組みに関して、「詳しく知りたい」という方も中にはいるかと思います。
今回は、審美歯科治療の治療内容に関する疑問を解決していきたいと思います。
〇ホワイトニングで歯が不自然に白くなることはある?
ホワイトニングを行うにあたって、「不自然に白くなりすぎることはあるのか?」と心配する方は多いです。
治療後の白さに関しては、ホワイトニングの方法や時間によって多少変わってきますが、1回のホワイトニングで心配するほど真っ白になることはありません。
通常、ある程度歯を白くするためには、ホワイトニングを数回繰り返す必要があります。
また、治療を行う前に、どの程度の白さにするか医師に相談してから治療するため、明らかにホワイトニングを行ったとわかるような、不自然な白さになる心配はありません。
そのため、「誰にもホワイトニングを受けたことがばれたくない」という方も、安心して治療を受けることができます。
〇歯並びが悪くてもホワイトニングを受けることは可能?
審美歯科治療の1つであるホワイトニングの治療内容に関し、「歯並びが悪くても審美歯科治療を受けることができる?」という疑問を持つ方は多いです。
ごく稀に、ホワイトニングの薬液をうまく塗布できなかったり、ライトを照射できなかったりするケースがありますが、基本的には歯並びの良し悪しに関係なく、ホワイトニングを受けることができます。
ただし、歯並びの状態によっては、歯垢や着色汚れが溜まりやすいことがあり、そのような場合は歯が白くなった後も定期的なメンテナンスが大変になるため、先に歯列矯正で歯並びを良くする必要が出てくるかもしれません。
〇ホワイトニングとクリーニングはどう違うのか?
代表的な審美歯科治療であるホワイトニング、クリーニングにおける治療内容の違いに関しても、疑問を抱く方は多いです。
ホワイトニングは、歯の内部を漂白し、白い歯を手に入れる治療であるのに対し、クリーニングは歯の表面に付いた着色汚れを除去し、歯を本来の色に戻すというものです。
そのため、前もってクリーニングを受けておかないと、ホワイトニングの効果が正しく得られないこともあります。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・1回のホワイトニングで、不自然なほど明らかに歯が真っ白になることはない
・歯並びが悪くてもホワイトニングを受けることは可能
・あまりに歯並びが悪い場合、ホワイトニング前の歯列矯正を勧められる可能性はある
・代表的な審美歯科治療のホワイトニングは歯を白くすること、クリーニングは歯を本来の色に戻すことが治療内容
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。