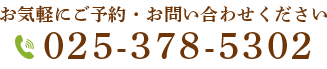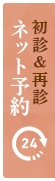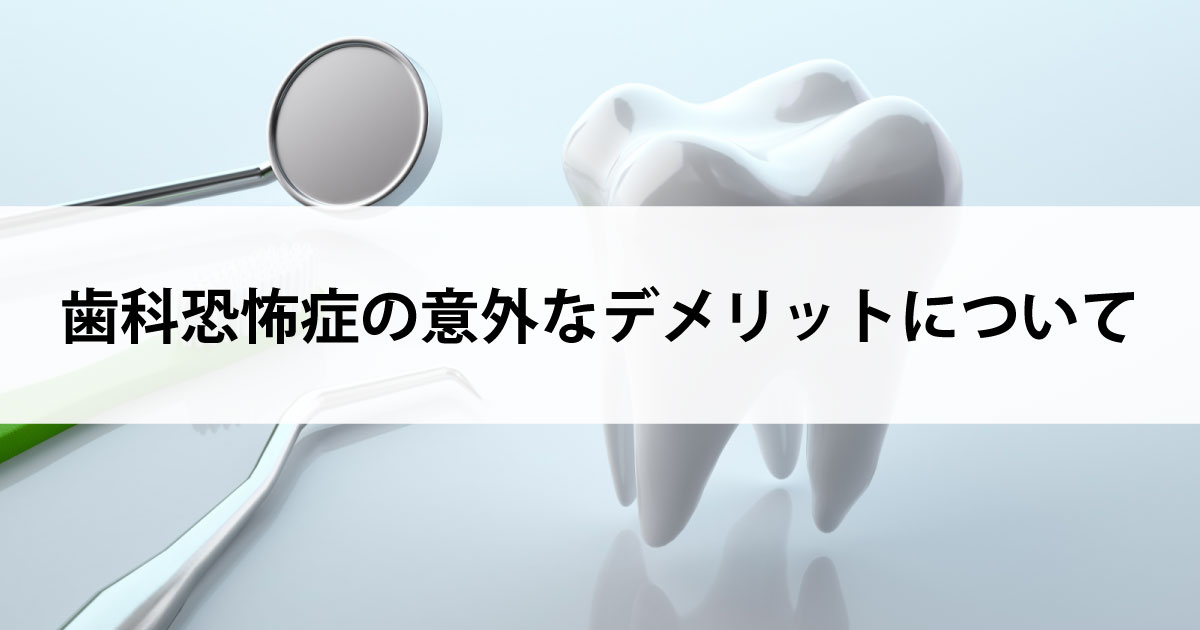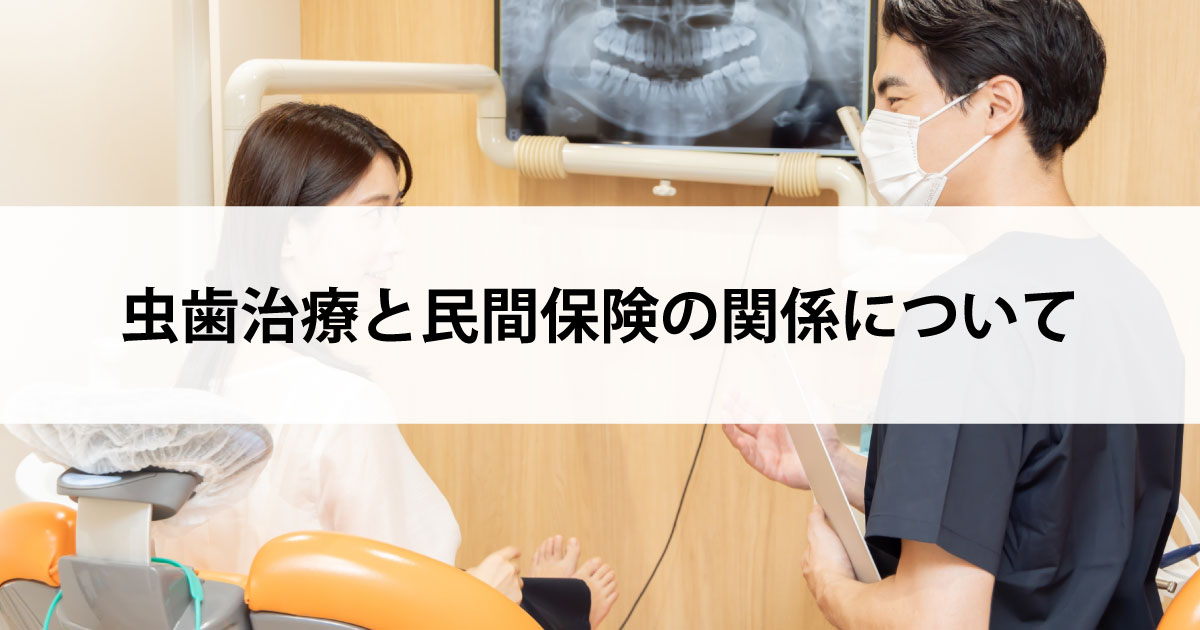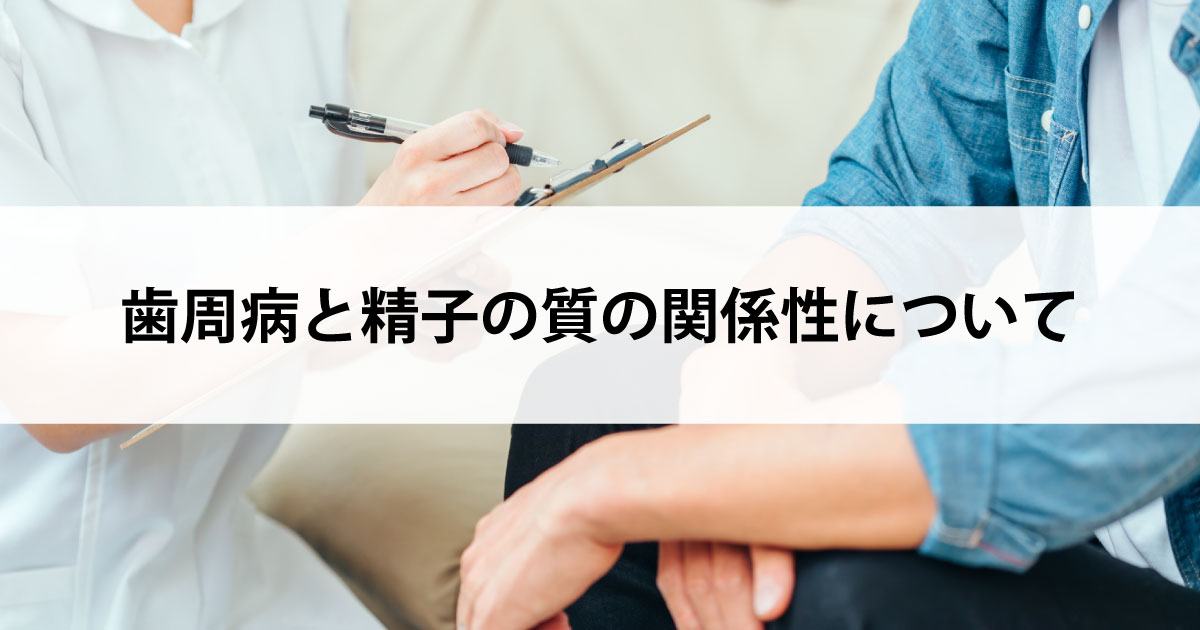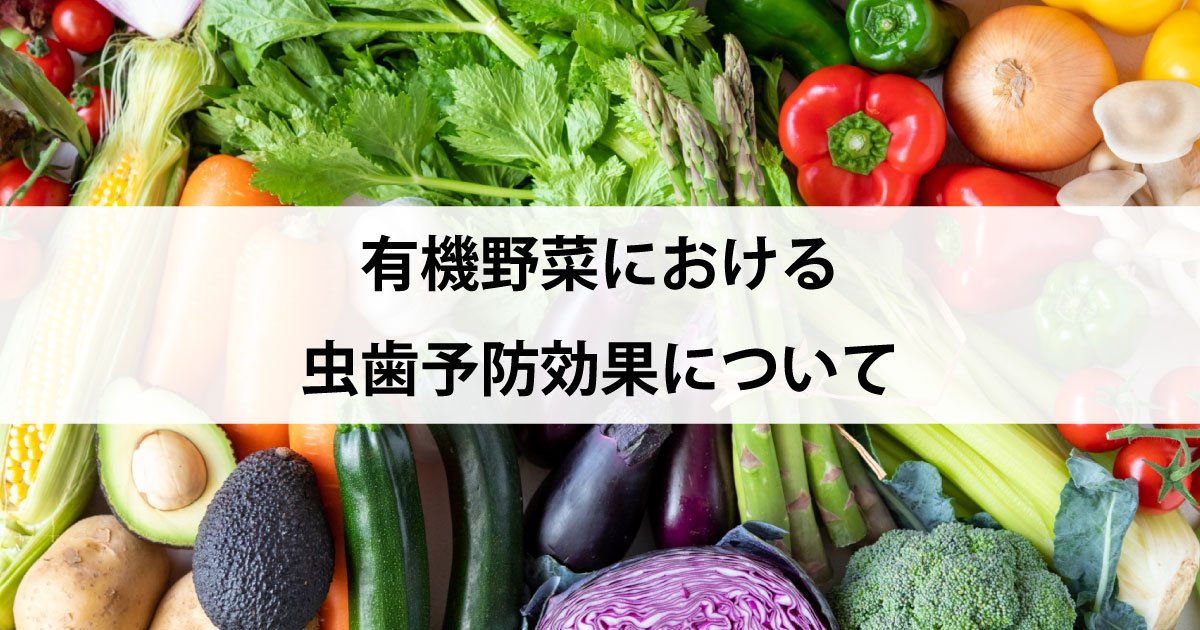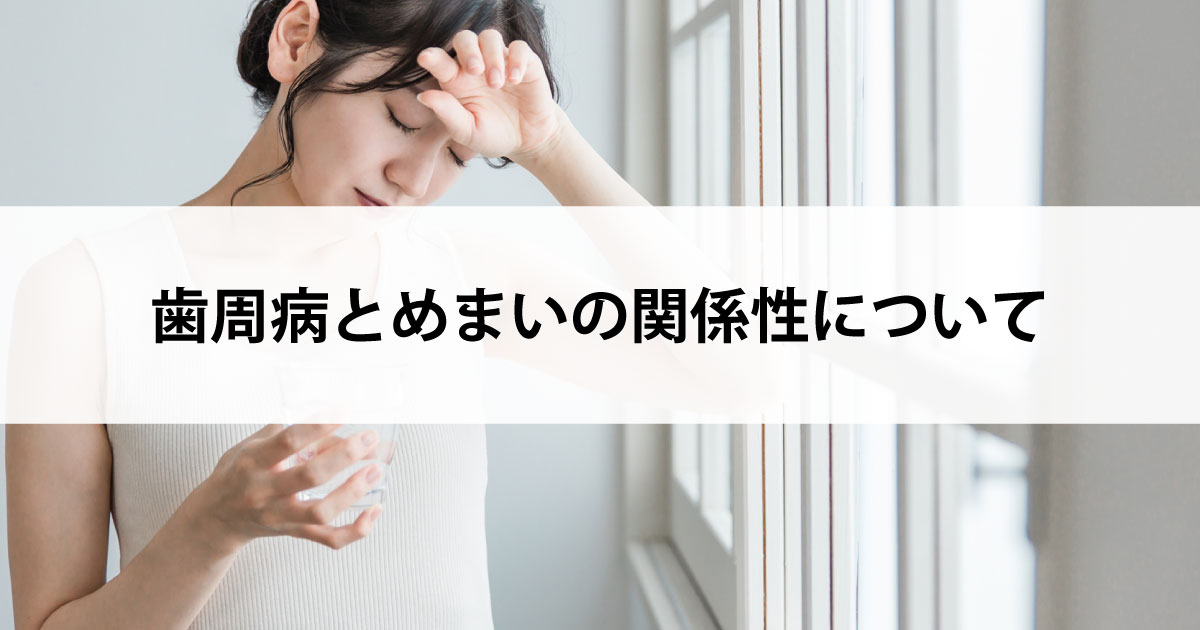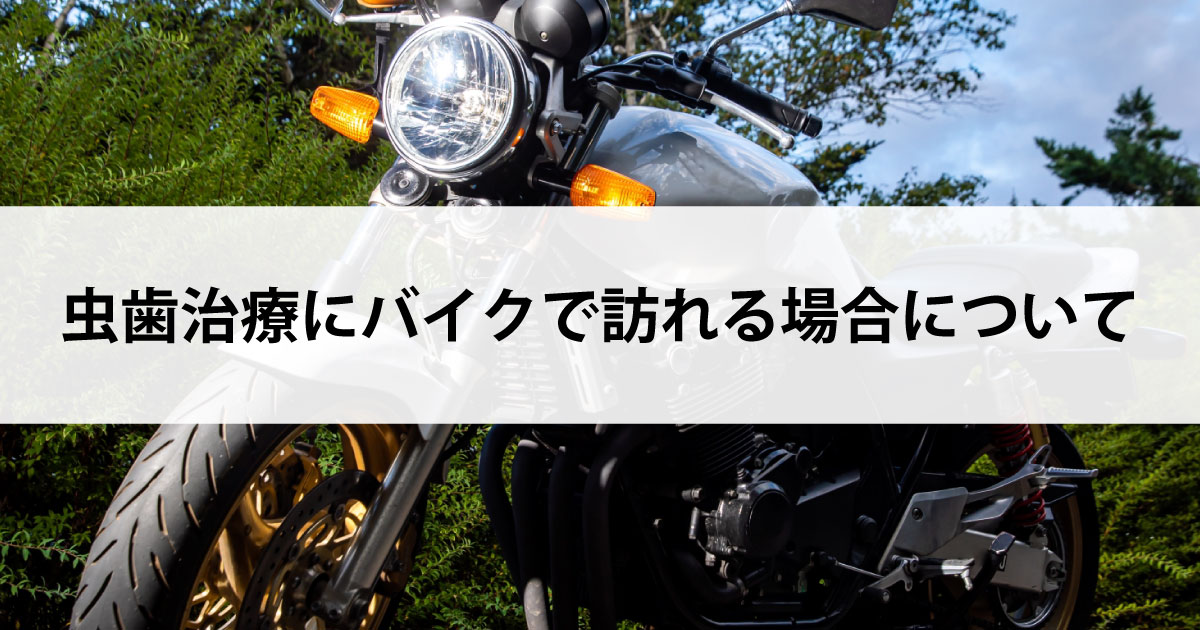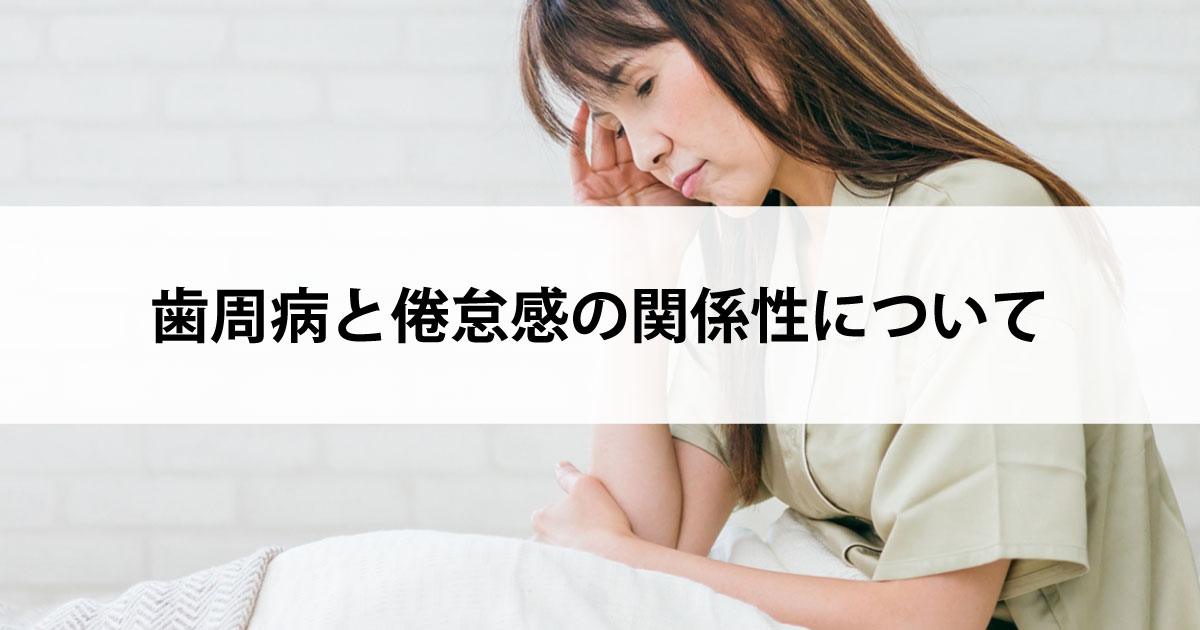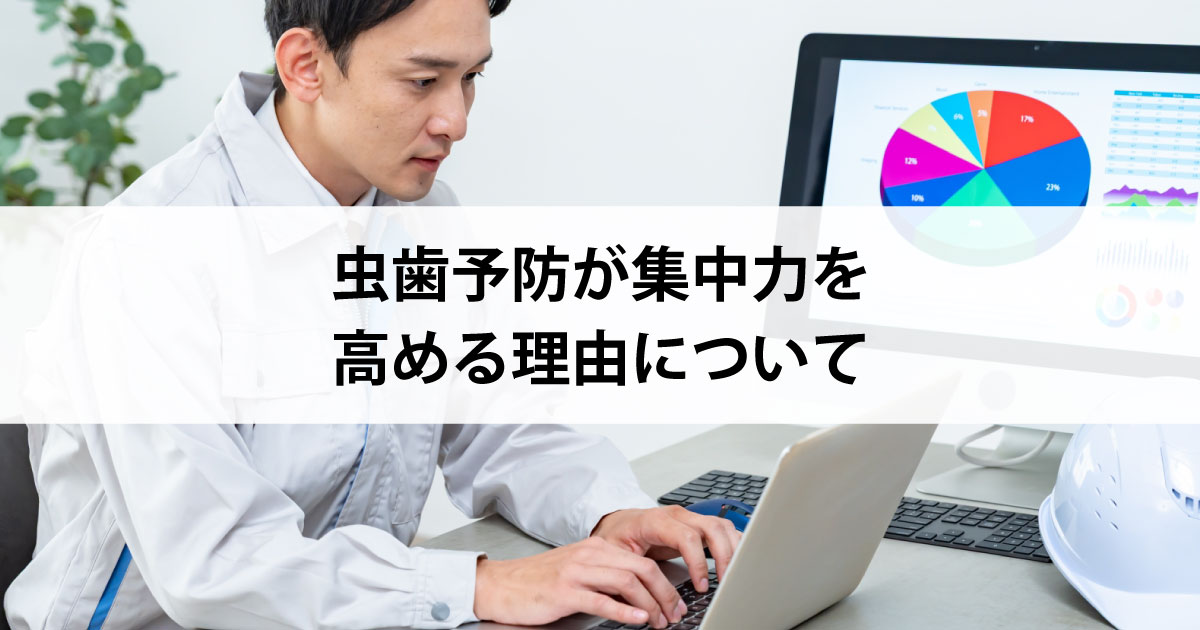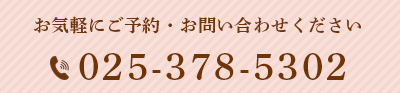歯科恐怖症は、過剰に虫歯治療もしくは歯科クリニック自体に恐怖心を覚え、通院するのが困難になってしまう症状です。
過去の治療で辛い思いをした方などによく見られますが、恐怖心があるからといって通院しないと症状はさらに悪化します。
また歯科恐怖症には、他にも意外なデメリットがあります。
治療費の大幅な上昇
歯科恐怖症の意外なデメリットとしては、まず治療費の大幅な上昇が挙げられます。
恐怖心から虫歯治療を先延ばしにすると、本来なら数千円程度で済むはずだった初期の虫歯治療が、神経の治療やインプラント治療が必要な段階にまで悪化します。
さらに極めて稀なケースですが、強い歯科恐怖症で全身麻酔による治療を選択する場合、1回あたり10万円程度の追加費用が発生することもあります。
そのため、すぐに治療は受けられない状態であっても、まず相談だけはするべきです。
就ける職業が制限される
就ける職業が制限されるという点も、歯科恐怖症の意外なデメリットです。
虫歯治療や歯科クリニックに恐怖心を抱く方の中には、まだ10代の若い方もいるでしょう。
また若い方の中には、今後パイロットや宇宙飛行士などの職業に就きたいと考える方もいるかと思います。
しかし航空法などの規定により、パイロットや宇宙飛行士などは“航空業務に支障をきたすおそれのある疾患がないこと”が条件とされる場合があります。
ここでいう航空業務に支障をきたす疾患には、虫歯が含まれています。
これらの職業に就く場合、気圧の変化で虫歯が激痛を引き起こすリスクがあるため、いつまでも通院しないでいると理想の職業を目指せなくなる可能性があります。
選択肢の消失
歯科恐怖症の方は、今後の治療における選択肢が消失するおそれもあります。
通院が怖いがために虫歯を放置していると、重度にまで進行し、土台となる顎の骨が吸収されてしまうことがあります。
またこのような状態だと、いざ勇気を出して治療しようと思っても、インプラント治療などの硬度な治療が受けられなくなる場合があります。
“お金を払えば治る”という段階を過ぎてしまうのは、とても大きな損失です。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯科恐怖症であるために虫歯治療を先延ばしにすると、治療費が大幅に上昇する可能性がある
・虫歯を放置した状態だと、規定によりパイロットや宇宙飛行士といった職業に就けなくなる
・歯科恐怖症で通院できない間に症状が悪化すると、治療の選択肢が消失するおそれがある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。