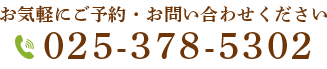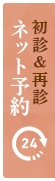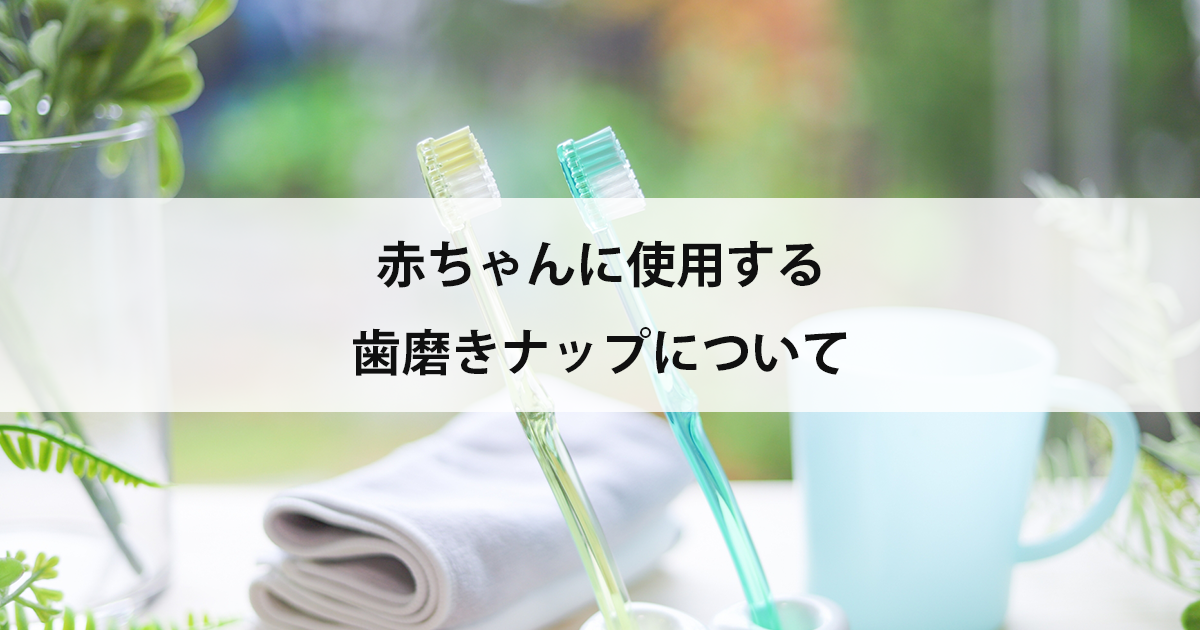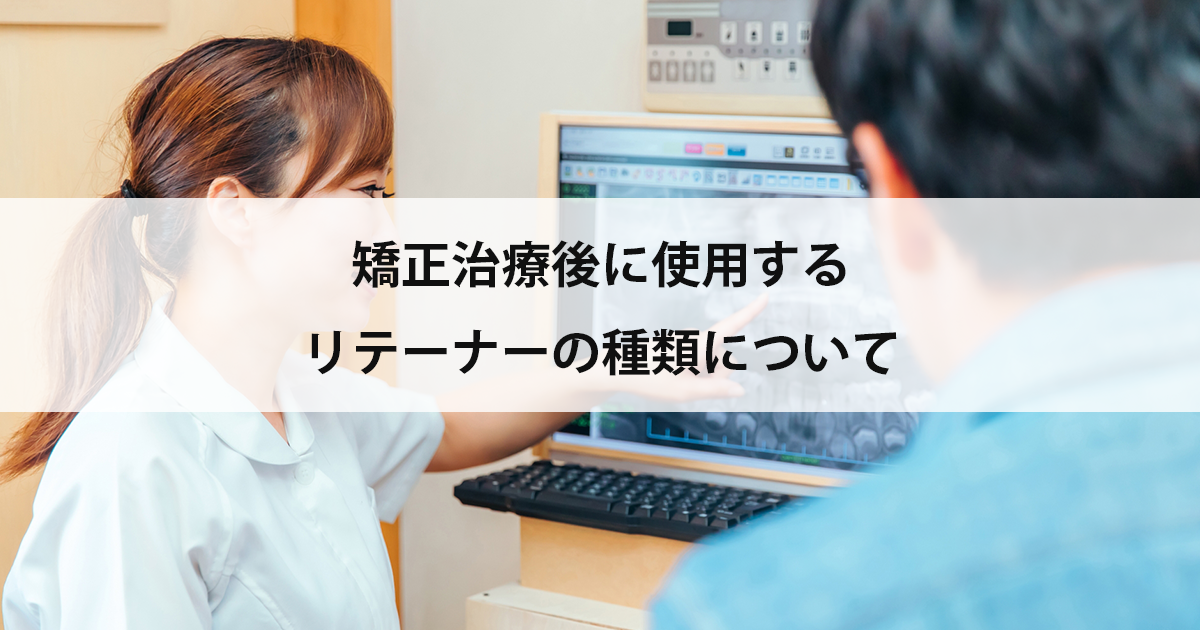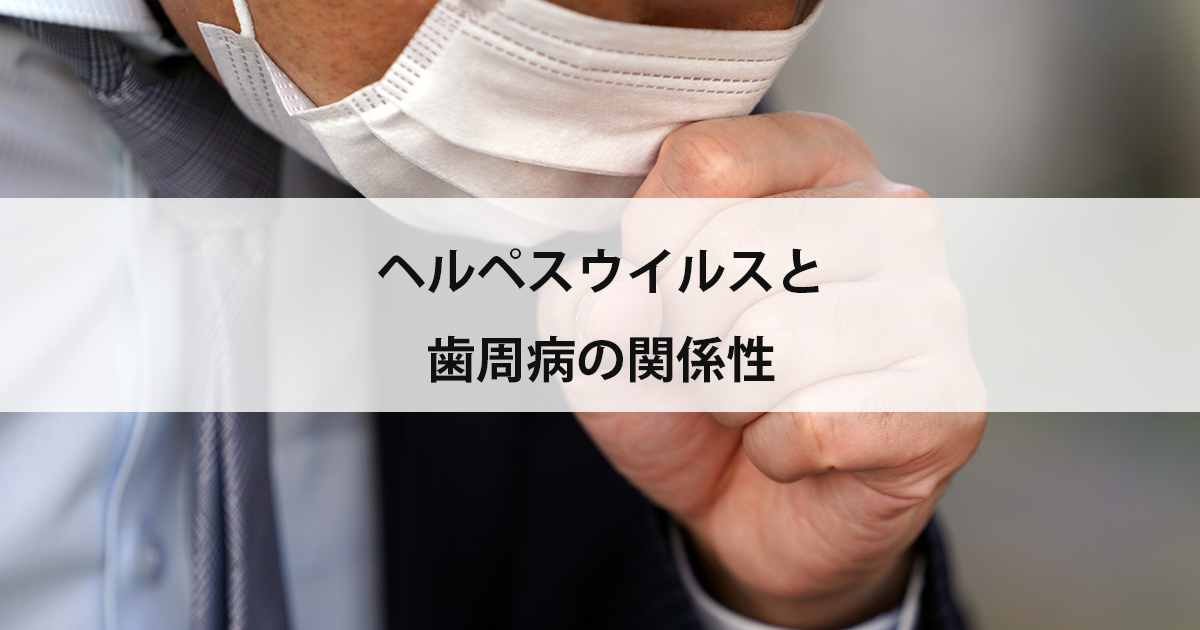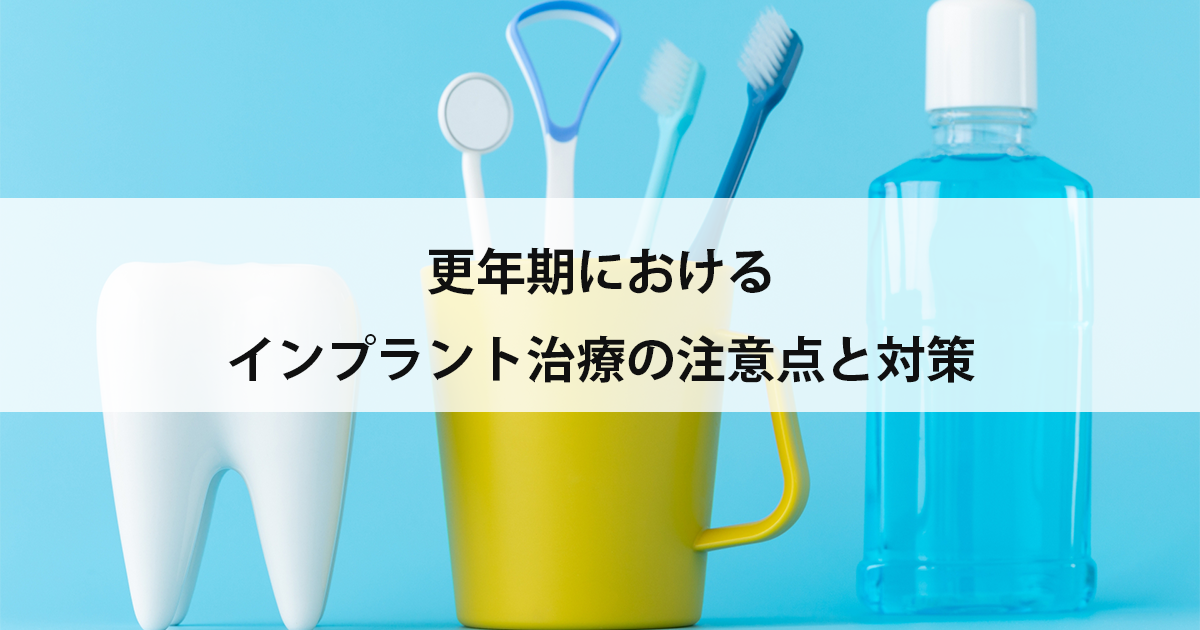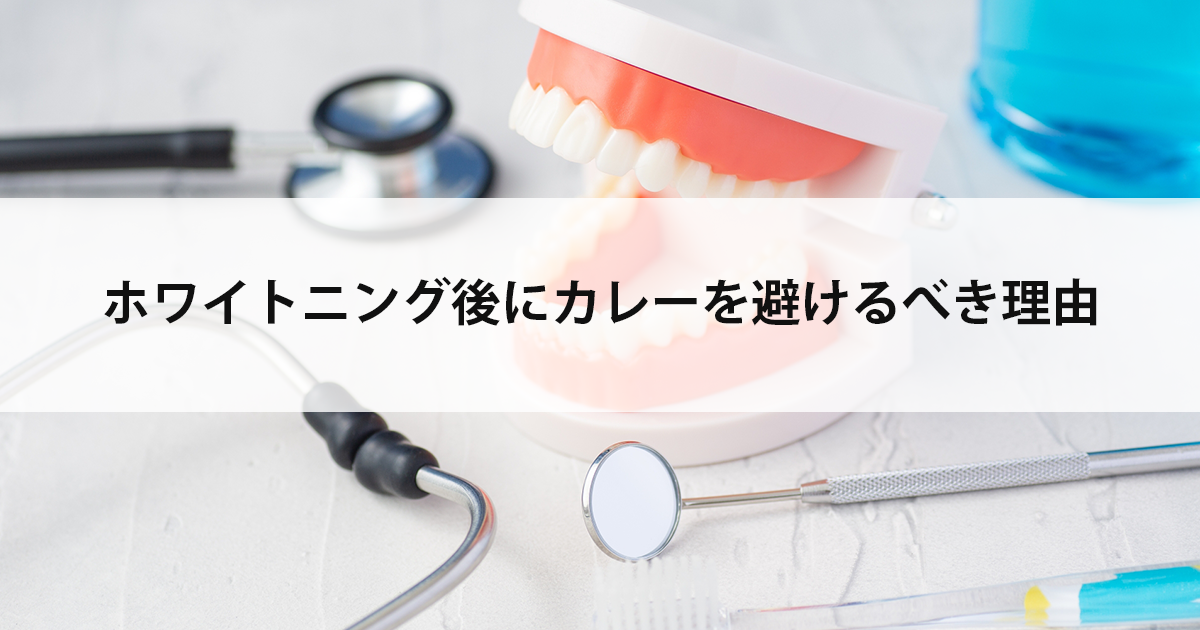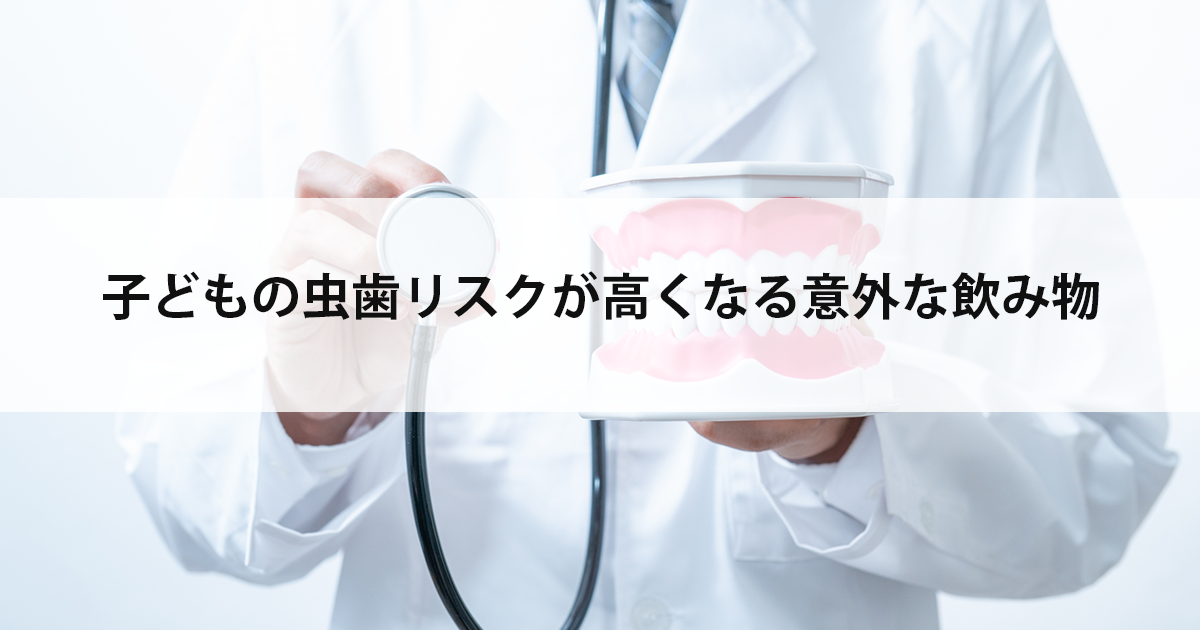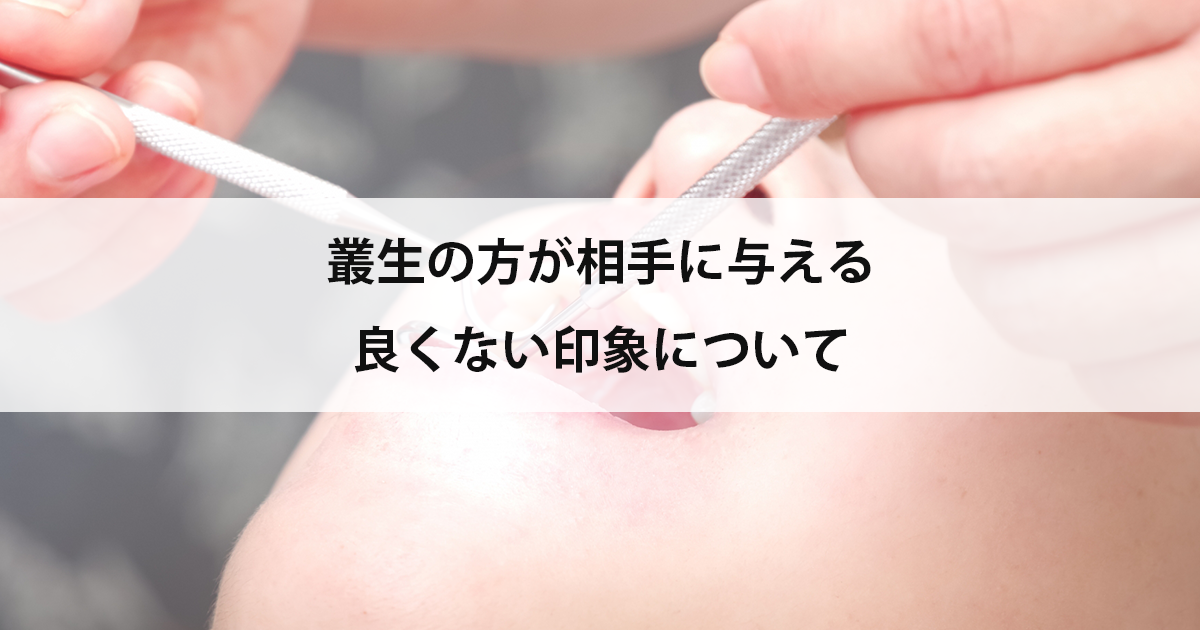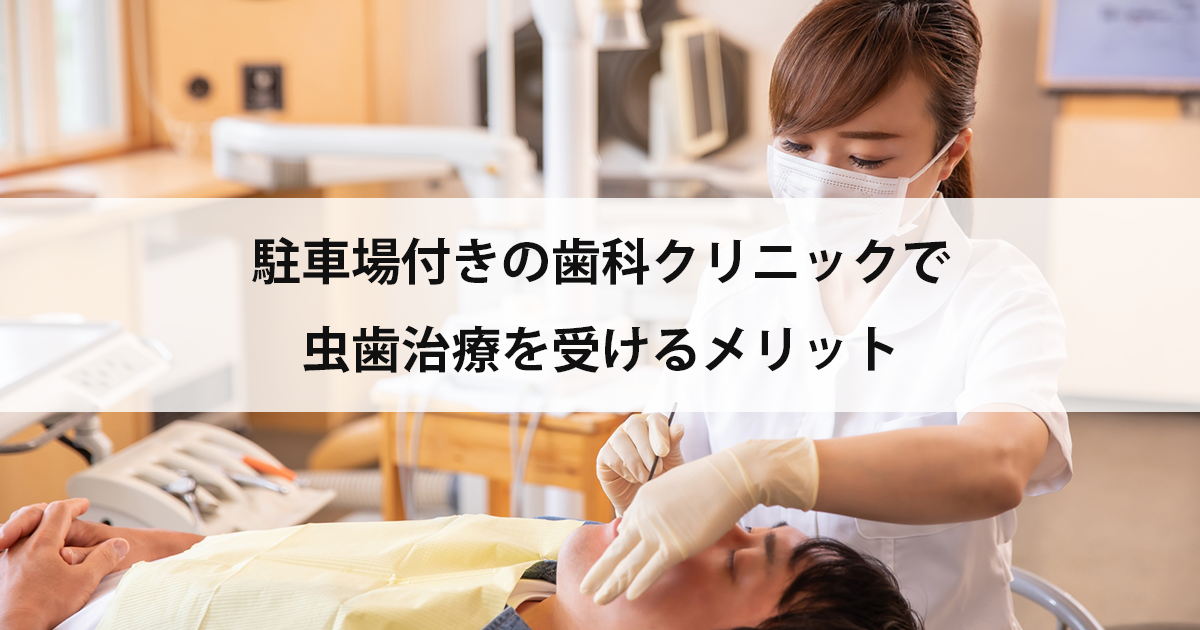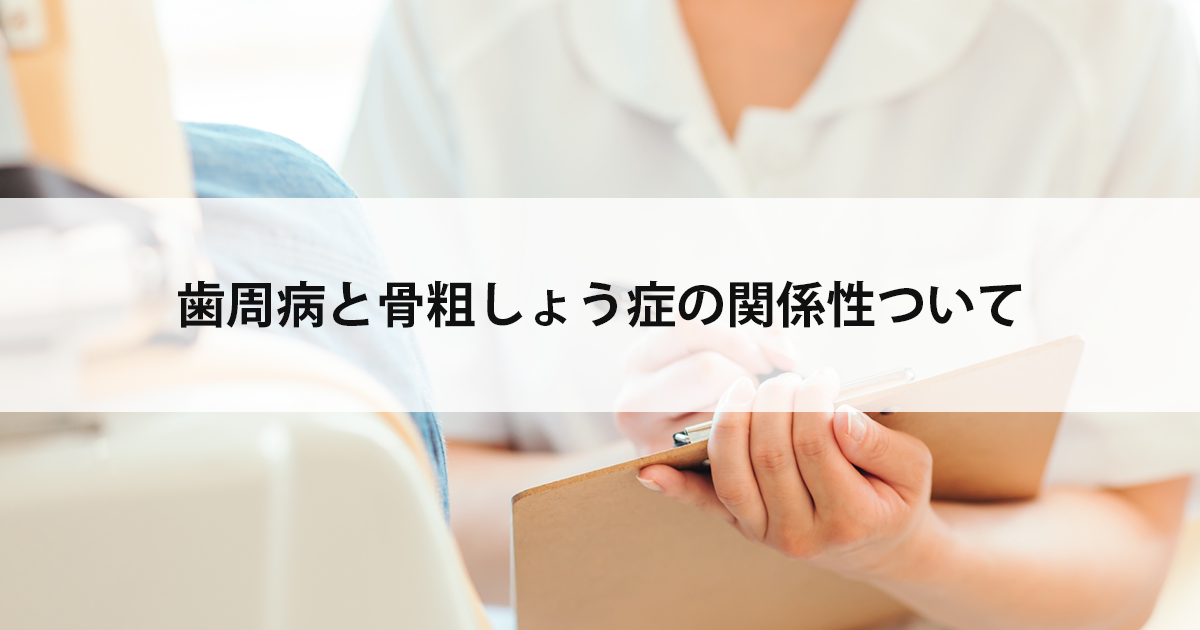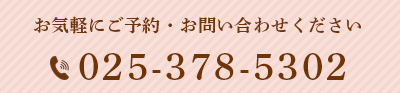まだ歯が生えたばかりの赤ちゃんに対しては、歯ブラシではなく歯磨きナップを使用して口内ケアを行います。
歯磨きナップは、ブラシではなくシートタイプのデンタルケア商品であり、親御さんは詳細を把握しておく必要があります。
今回は歯磨きナップの特徴や使い方、注意点などについて解説します。
歯磨きナップの特徴
歯磨きナップは、ウェットタイプのデンタルケア商品です。
濡れたシートで赤ちゃんの歯の汚れを拭き取れるため、手軽に口内ケアができます。
また歯磨きナップの多くは、キシリトールが配合されています。
キシリトールは、虫歯の原因となる酸をつくらないため、安心して使用できます。
さらにノンアルコール・無着色・無香料・防腐剤不使用のため、赤ちゃんの身体に影響が出ることはまずありません。
ちなみに商品によっては、緑茶ポリフェノールなどが配合されているものもあります。
歯磨きナップの使い方
赤ちゃんに歯磨きナップを使用する際は、まず個包装されているところから1枚取り出します。
このとき、開封したものはすぐに使用するのがポイントです。
その後、取り出した歯磨きナップを赤ちゃんの歯や歯茎に優しくこすりつけます。
歯の表面だけでなく、裏側も忘れずに拭きましょう。
最後に、使用した歯磨きナップを破棄します。
詰まりの原因になるためトイレに流すことはせず、一度使用したものは繰り返し使わないように注意してください。
歯磨きナップの注意点
赤ちゃんの口内に傷などの異常がある場合、その部位には歯磨きナップを使用してはいけません。
赤ちゃんの粘膜は非常に繊細であるため、少し拭いただけでも症状が悪化してしまう可能性があります。
また歯磨きナップは基本的に防腐剤不使用のため、個包装に傷がつくとナップにカビ等が生えることが考えられます。
そのため、個包装の状態で持ち歩く際は、傷がつかないように細心の注意を払いましょう。
さらに、歯磨きナップを使用することで発疹などの異常が現れた場合、すぐに使用を中止します。
症状が改善しない場合、歯科クリニックや小児科、皮膚科などのクリニックを受診してください。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯磨きナップは赤ちゃんのデンタルケア商品で、歯や歯茎を拭いて使用する
・ノンアルコール・無着色・無香料など赤ちゃんでも安心して使用できるものが多い
・歯磨きナップを使用するときは、歯の表面だけでなく裏側も忘れずに拭く
・歯磨きナップは防腐剤不使用のため、個包装で持ち歩く場合は傷がつかないように注意する
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。