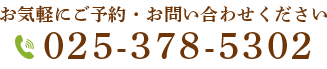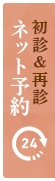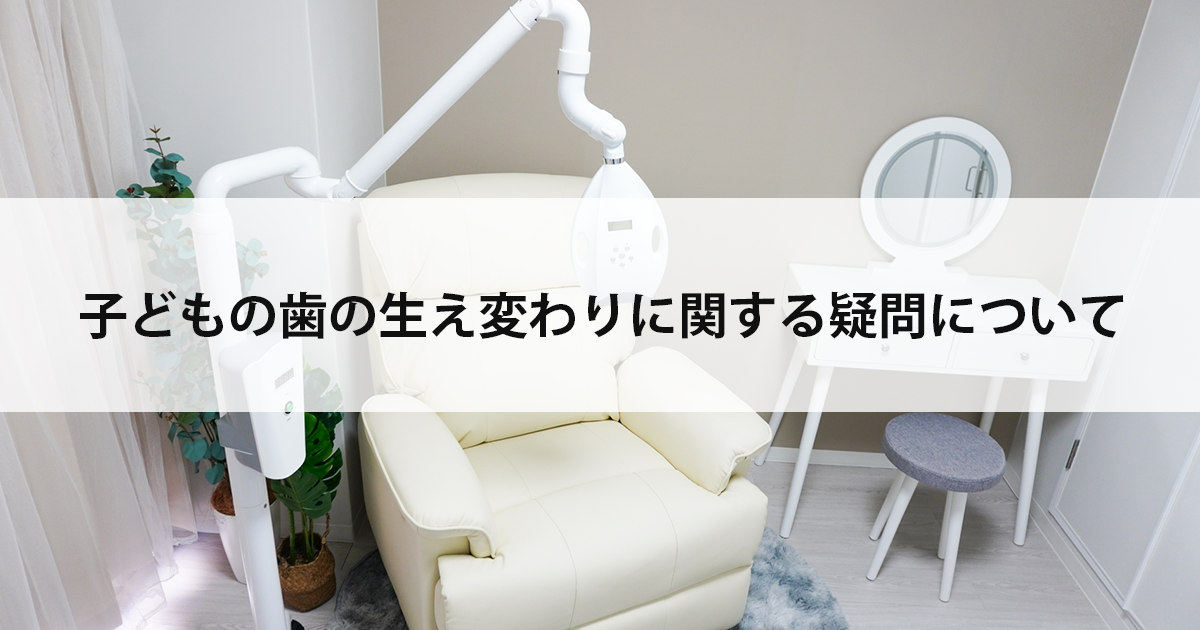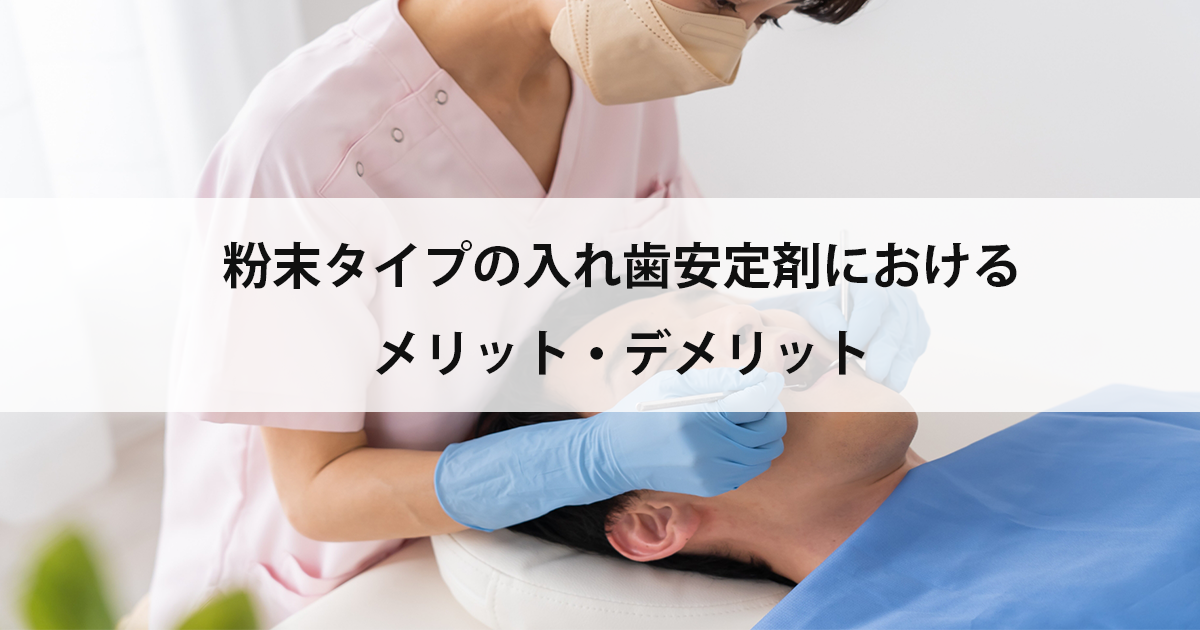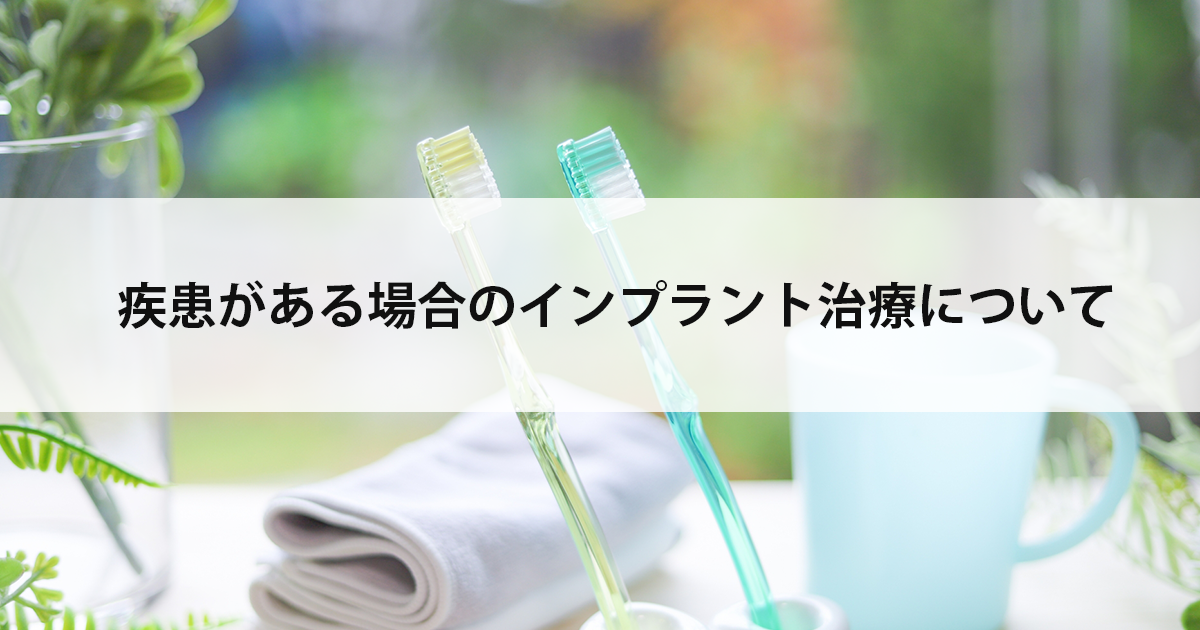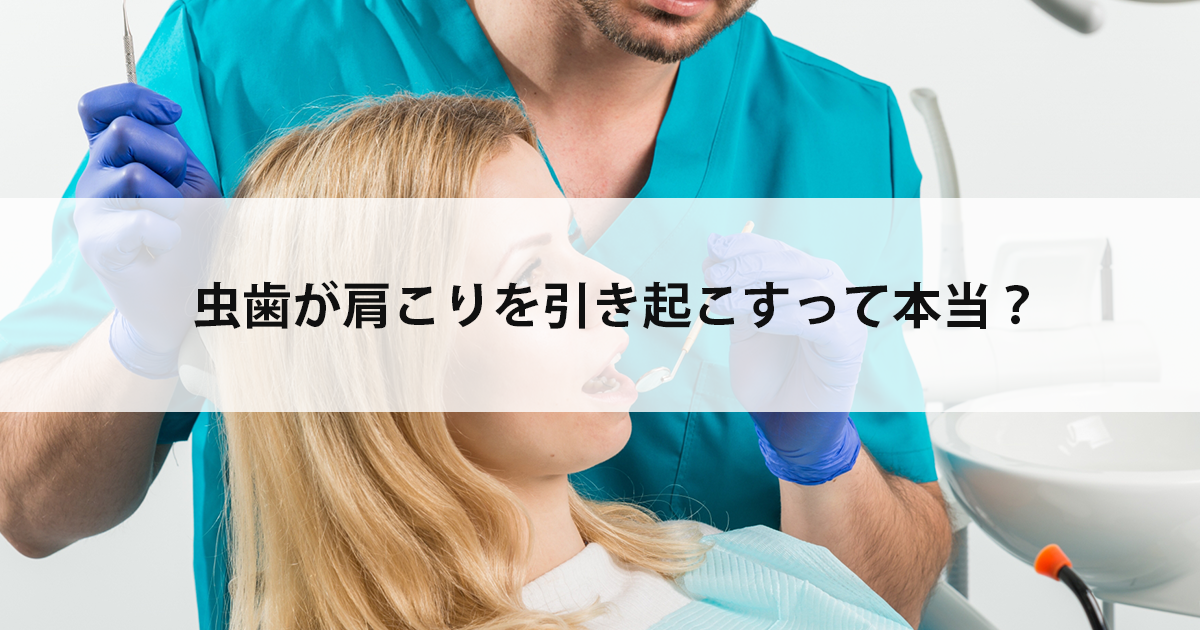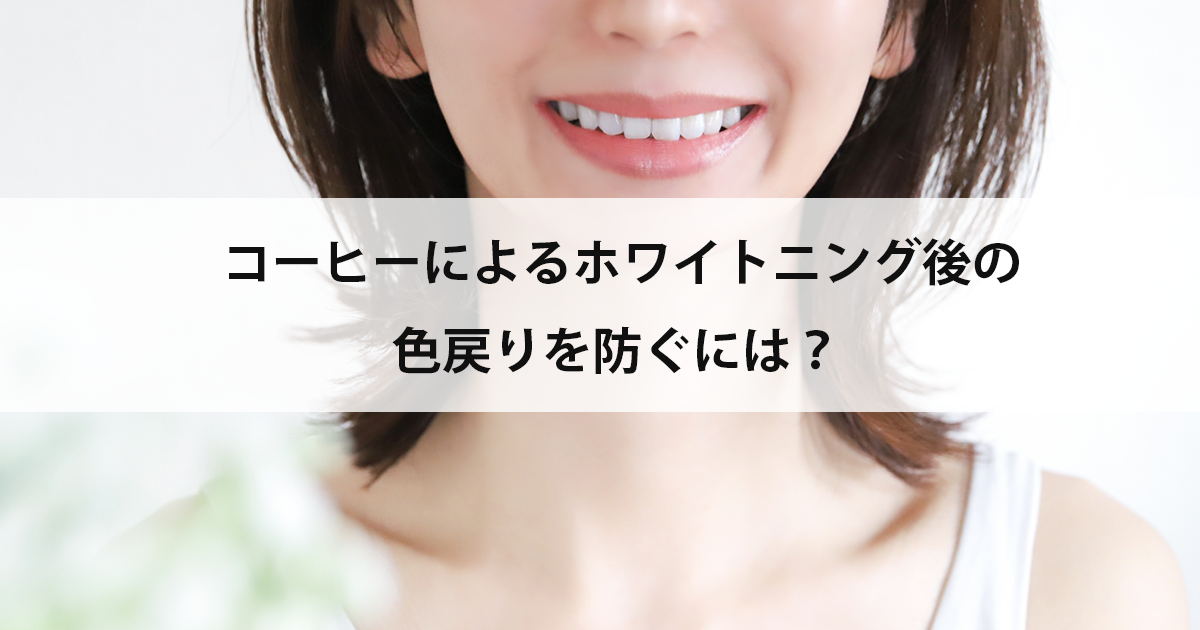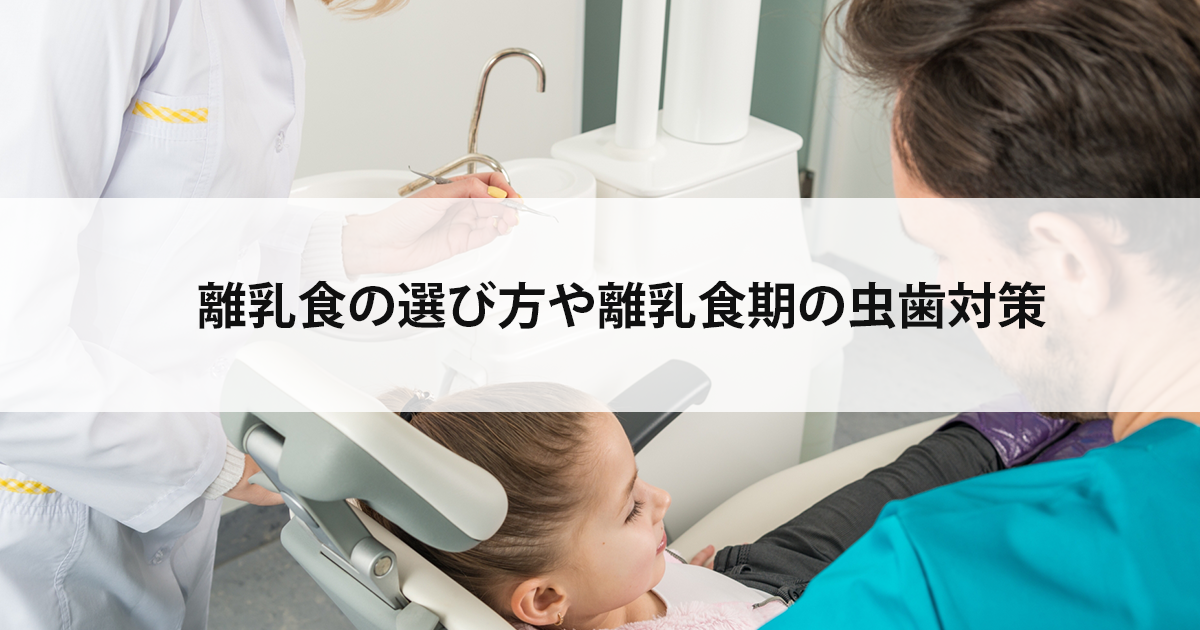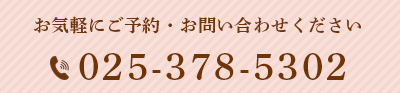ホワイトニングを受けた後は、食事の内容に気を付けなければいけません。
以前のように何でも好きなものを食べたり飲んだりすると、せっかく白くなった歯が色戻歯してしまうおそれがあります。
今回は、ホワイトニング後にルイボスティーを飲むメリットを中心に解説します。
〇ルイボスティーとは?
普段緑茶や麦茶を飲む機会が多いという方は、ルイボスティーにあまり馴染みがないかもしれません。
ルイボスティーは、南アフリカのセダルバーグ山脈で栽培される、マメ科の低木であるアスパラサス・リネアリスの葉を原料としたお茶です。
ノンカロリーであり、ストレートでもミルクやフルーツと合わせても楽しめるのが特徴です。
また麦茶と同じくカフェインが含まれていないため、カフェインの影響を避けるべきとされる妊娠中の女性に好まれる傾向にあります。
〇ホワイトニング後にルイボスティーを摂取するメリット
ルイボスティーは、ホワイトニング後に摂取する飲み物としては非常におすすめです。
なぜなら、着色のリスクが低いからです。
ルイボスティーには、歯に色素が沈着する原因となるタンニンがそれほど含まれていません。
またカフェインも、歯の表面に色素を沈着させる原因になるため、ノンカフェインのルイボスティーはメリットが大きいです。
さらに、ルイボスティーには抗酸化作用もあります。
ホワイトニング後は、歯の表面のペリクルという膜が剥がれていて、刺激を受けやすい状態になっています。
そのため、ルイボスティーを摂取して歯へのダメージを抑えることが大切です。
〇ルイボスティーの飲み方について
ルイボスティーを摂取する際は、ホワイトニング後に摂取するものとしてのメリットを活かすために、煮出して飲むのがおすすめです。
水出しよりも煮出しの方が、抗酸化作用のあるフラボノイドを抽出しやすくなります。
具体的には、まずルイボスティーの茶葉を5g用意します。
こちらを1リットルの沸騰したお湯に入れ、10分程度煮出します。
最後に火を止めて、茶葉を取り出したら完成です。
もちろん時間がない方は、コンビニなどで完成したルイボスティーを購入して飲んでも構いません。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・ルイボスティーは南アフリカ原産のお茶
・ルイボスティーには着色成分であるカフェインが含まれておらず、タンニンの含有量も少ない
・ルイボスティーには歯を刺激から守る抗酸化作用もある
・ルイボスティーを飲む際は、メリットを活かすために煮出して飲むのがおすすめ
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。