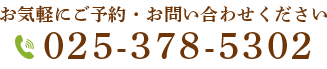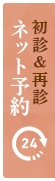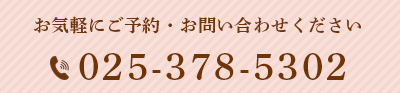自身が思っている以上に、周りの方に口臭が伝わっているというケースは非常に多いです。
また、こちらは食事や虫歯、歯周病といった口内トラブルなど、さまざまな原因で発生しますが、飲み物を飲むことで程度改善できます。
ここからは、口臭の改善効果のある飲み物について解説します。
〇まず意識したいのは水、緑茶の摂取
口臭を改善できる飲み物としてもっともメジャーなのは、やはり水や緑茶です。
適度な水の摂取は、口内の乾燥を防止し、唾液分泌を促す効果があるため、口臭予防にはとても効果的です。
具体的には、朝食前や就寝前(歯磨き後)に300cc程度の水を飲むことで、口臭の程度は大きく変わってきます。
また、緑茶に含まれる茶カテキンは、虫歯菌に対して抗菌性を示し、歯垢の元となる口内の粘着性グルカンを作る酵素(グルコシルトランスフェラーゼ)の働きを押さえ、虫歯や口臭を防いでくれます。
〇意外な口臭改善効果を発揮するのはココア
口臭を改善できる意外な飲み物としては、ココアが挙げられます。
ココアは、ポリフェノールが豊富な抗酸化食品として知られていて、実際に2週間のココアの飲用で、歯周病関連菌の数および呼気に含まれる口臭成分(揮発性硫黄化合物)がともに減少することが報告されています。
飲み方としては、何も入っていないピュアココア8gを100mlの水かお湯で溶かし、1日3回毎食後に飲むのが効果的です。
また、飲みやすいよう糖類ゼロの甘味料を加えても良く、飲用後1時間はうがい、歯磨きを避けます。
もちろん、通常の砂糖を入れると虫歯菌が増加し、かえって口臭が強くなるおそれがあるため、注意が必要です。
〇口臭がひどくなる飲み物について
逆に口臭がひどくなってしまう飲み物としては、主に以下のものが挙げられます。
・コーヒー
・エナジードリンク
・甘いジュース
コーヒー豆の細かい粒子は、舌の表面に付着しやすく、こちらが舌苔となって残ることにより、口臭につながることがあります。
また、コーヒーには利尿効果のあるカフェインが多く含まれていて、こちらは口内の乾燥、口臭悪化の原因になります。
こちらは、エナジードリンクにも同じことが言えます。
もちろん、砂糖が大量に含まれているジュースや炭酸飲料も、唾液の分泌を阻害する原因となります。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・適度な水の摂取は口内の乾燥を防止し、唾液分泌を促すため、口臭改善には効果的
・緑茶に含まれる茶カテキンには、虫歯菌に対する抗菌性、口臭改善効果がある
・ピュアココアに含まれるポリフェノールは、口臭成分を減少させる
・コーヒーやエナジードリンク、甘いジュースなどは口臭が気になる方が避けるべき飲み物
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。