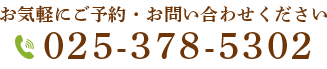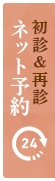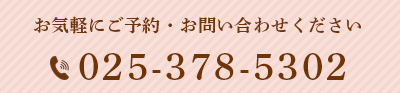子どもの虫歯治療を行った後は、大人の虫歯治療と同様に、施術箇所に詰め物を入れて対応します。
しかし、子どもの詰め物は大人と比べて取れやすいため、注意しなければいけません。
今回はこちらの理由と、詰め物が取れてしまった場合に避けるべき対処法について解説したいと思います。
〇子どもの詰め物が取れやすいのはなぜ?
ここでいう子どもの詰め物とは、永久歯ではなく乳歯に入れる詰め物のことを指しています。
乳歯は永久歯と比べて薄く、詰め物自体も同じように薄くなってしまうため、どうしても取れやすくなります。
また、硬さに関しても永久歯より劣るため、最初は同じ高さに詰め物をしていても、周囲の乳歯が擦り減ることにより、詰め物だけが出っ張り、食事の際などにひっかかって取れることが考えられます。
その他、生え変わりの時期にも、子どもの詰め物は取れやすくなります。
生え変わりの時期は、歯が動いたり、施術箇所の隣に歯が生えてきたりするため、そちらの影響を受け、詰め物が取れる可能性があります。
ちなみに、唾液の分泌量が多いことも、子どもの詰め物が取れやすい理由の1つです。
詰め物には、歯に固定するためのセメントが使用されていますが、唾液が多いとこちらの接着力が弱くなります。
〇詰め物が取れた場合に避けるべき対処法
もし、子どもの詰め物が取れてしまったのであれば、家庭にあるもので元に戻そうとしたり、外れたまま放置したりしてはいけません。
例えば、瞬間接着剤などを使用して無理に戻そうとすると、歯茎などを傷つけるおそれがありますし、誤って粘膜などにくっついてしまうと、こちらを剥がすための治療を受けなければいけない可能性もあります。
そのため、取れた詰め物はチャック付きのビニール袋などで保管し、早急に歯科クリニックに連絡して対応してもらいましょう。
また、詰め物が取れたまま放置すると、穴が開いている部分から細菌が入ったり、詰め物が合わなくなり、一から型取りをしなければいけなくなったりすることもあります。
そして、歯科クリニックを訪れるまでの間は、詰め物が取れてしまった方の歯で咀嚼をしてはいけません。
詰め物をしていた部分に穴が開いた状態で咀嚼すると、食べカスや歯垢が溜まりやすくなり、虫歯の再発につながります。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・子どもの歯(乳歯)は永久歯と比べて薄く柔らかいため、詰め物が取れやすい
・生え変わりの時期は、歯が動くことなどにより、詰め物も影響を受けやすい
・唾液の分泌量が多いことも、子どもの詰め物が取れやすい理由の1つ
・子どもの詰め物が取れても、自力で戻したり放置したりしてはいけない
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。