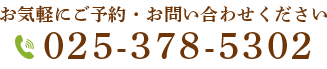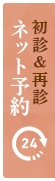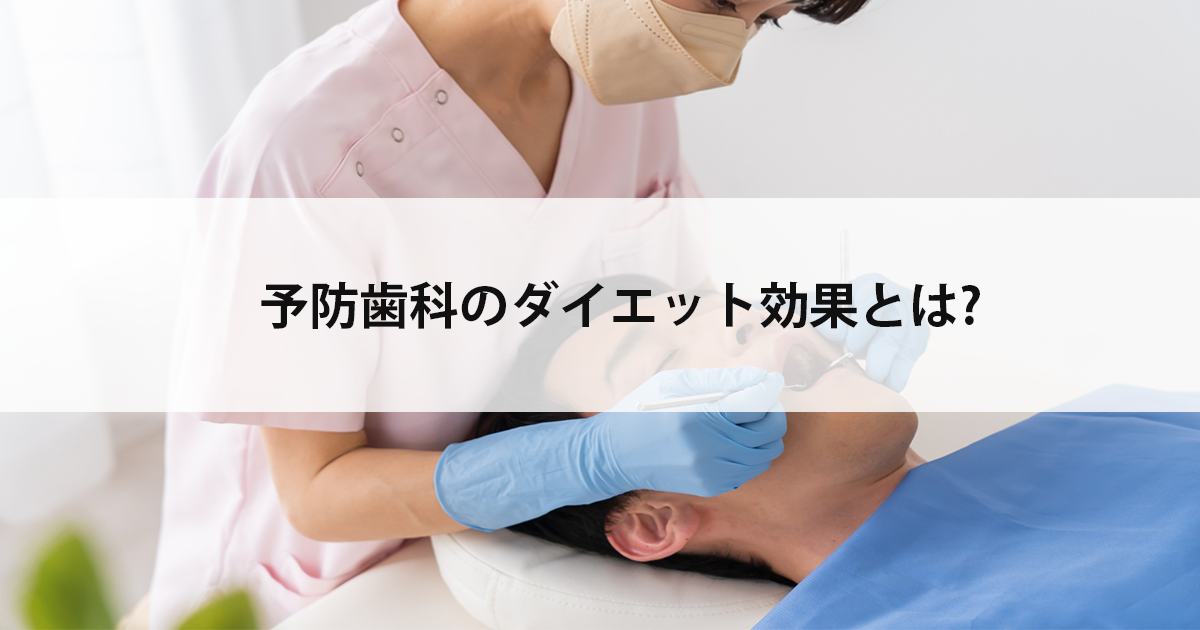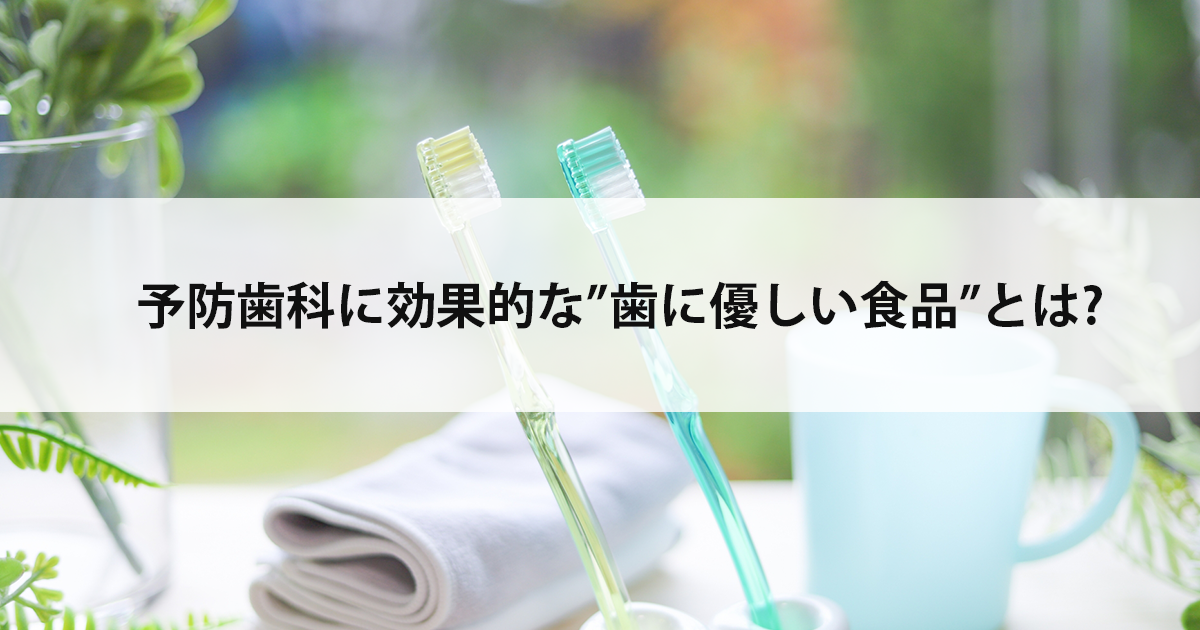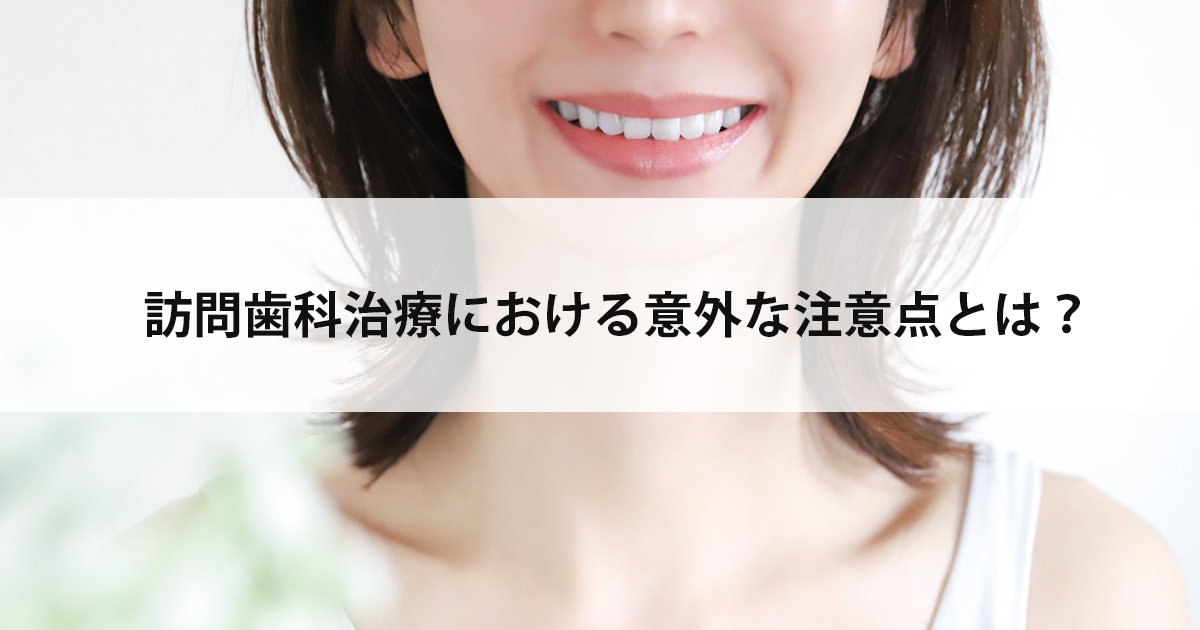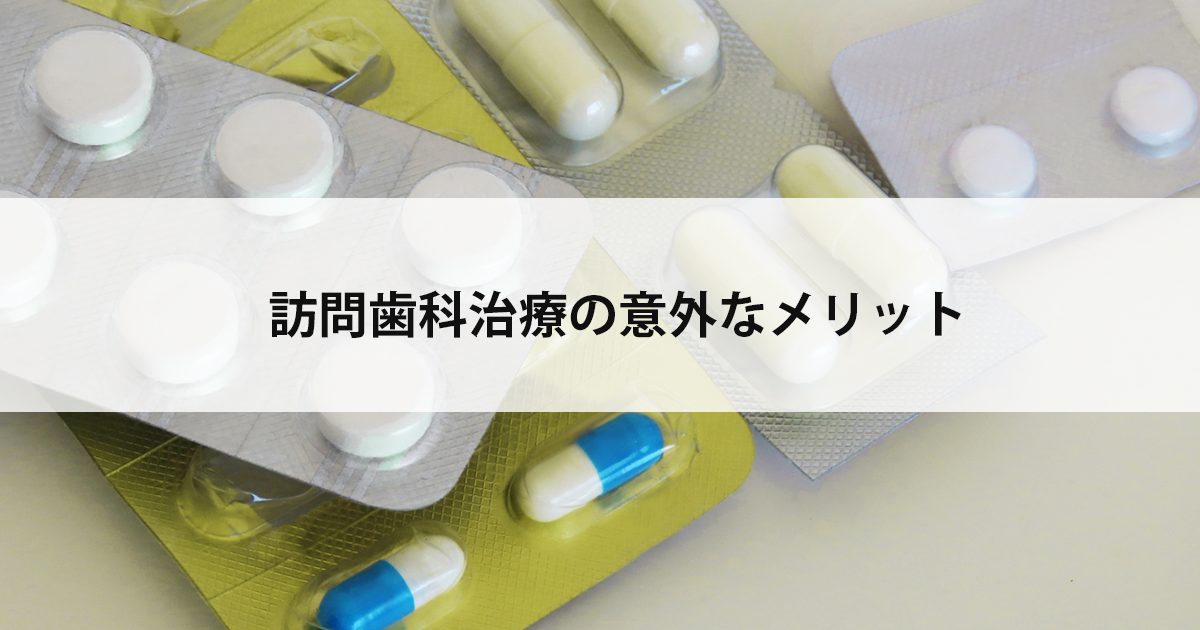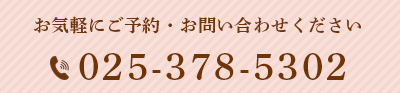裏側矯正はワイヤー矯正の一種であり、表側ではなく歯の裏側に矯正装置を装着します。
そのため、“目立たない矯正治療”として人気があります。
では、矯正装置が目立ってしまうことは本当にないのでしょうか?
今回は、裏側矯正が目立たない仕組みとあわせて、こちらの点について解説します。
〇裏側矯正が目立たない仕組み
裏側矯正が目立たないのは、外から見える部分に矯正装置がついていないからです。
通常のワイヤー矯正は表側矯正と呼ばれるもので、こちらは歯の表側にワイヤーとブラケットを装着するため、装置をつけていることが目立ってしまうという問題がありました。
裏側矯正は歯の裏側にワイヤーやブラケットがあるため、歯そのものが見えていても、外から矯正装置が見えることは基本的にありません。
またこのような理由から、人前に立つ職業や人と接することが多い職業などに就く方には重宝されています。
〇裏側矯正は本当に目立たないのか?
裏側矯正は、一般的な距離で普通に口を動かして会話をする程度であれば、目立つ可能性は極めて低いです。
しかし、相手の目の前で大きく口を開けて話したり、笑ったりする場合には矯正装置が見えてしまうことがあります。
もちろん、裏側矯正の装置が見えるほど至近距離で人と話す機会はなかなかありません。
また普通に口を開けている程度であれば、口の中を覗き込まれない限り、近い距離でも装置が見える可能性は低いです。
さらに裏側矯正の場合、装置の跡も歯の内側につくため、最終的に外したときにその跡が目立ってしまうこともありません。
〇目立たない代わりに発音がしづらくなる可能性がある
表側矯正の場合、ワイヤーやブラケットは歯の表側についているため、舌に装置が当たることはなく発音への影響は少ないです。
一方裏側矯正は舌が当たる内側に装置があることから、サ行やタ行、ラ行などの発音がしにくくなるおそれがあります。
発音は普段何気なく行っていますが、口周りの筋肉や舌の動きが非常に重要です。
そのため人前に立つことが多い職業であっても、会話をする機会が多い職業の場合、矯正開始からしばらくの間は支障が出るかもしれません。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・裏側矯正は歯の裏側に矯正装置がついているため、基本的に目立つことはない
・至近距離で口を大きく開けた場合などは、相手から矯正装置が見えることがある
・最終的に装置を外したときの跡も、裏側矯正であれば残りにくい
・裏側矯正は装置が目立ちにくい代わりに、発音がしづらくなる可能性がある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。