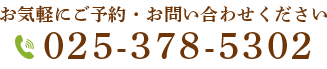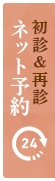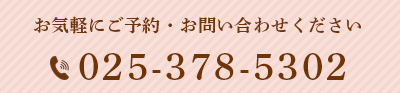虫歯予防を行うためには、甘いものなど虫歯リスクの高いものの摂取をなるべく控えなければいけません。
また普段お酒を飲む習慣がある方は、ビールや日本酒などではなく、焼酎を選ぶことが虫歯予防につながります。
今回は、焼酎の虫歯リスクが低い理由を中心に解説します。
焼酎の虫歯リスクが低いのはなぜ?
焼酎の虫歯リスクが低いのは、糖分がほとんど含まれていないからです。
こちらは、麦や芋などを原料に、蒸留してつくられることが理由です。
冒頭で少し触れたように、虫歯菌の大好物はなんといっても糖分です。
虫歯菌が糖分をエサに酸をつくり出すことで、歯が溶かされてしまい、虫歯が形成されます。
一方、ビールや日本酒などは醸造酒と呼ばれるもので、原料の発酵過程において糖分が残ります。
そのため、焼酎とは違って虫歯のリスクが高くなってしまいます。
pH値が中性に近いのもメリット
焼酎が虫歯になりにくいお酒である理由には、PH値が中性に近いということも挙げられます。
pH値は、液体が酸性かアルカリ性かを表す尺度であり、1~14までの数値で表記されます。
7が中性で、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性という扱いになります。
またpH値が低い酸性の飲み物は、歯のエナメル質を溶かし、虫歯のリスクを高めます。
例えば炭酸飲料やスポーツドリンク、柑橘類のジュースなどは酸性の飲み物に該当します。
一方、麦焼酎はpH値が約6.3と、限りなく中性に近いです。
ビールが4.0~4.4、日本酒が4.3~4.9であることを考えると、焼酎はかなり虫歯を防ぎやすいお酒だと言えます。
虫歯リスクを減らす焼酎の飲み方
焼酎の虫歯リスクをさらに軽減させるには、ストレートやロック、水割りで飲むことをおすすめします。
炭酸水で割ってしまうと、口内が酸性に傾いて虫歯のリスクが上昇します。
もちろん、ジュースなどの甘い割材を使用するのもNGです。
また焼酎を含むお酒は長時間飲んでしまいがちですが、ダラダラ飲むと口内が酸性に傾きやすくなります。
お酒を飲むときはおつまみも一緒に食べることが多いため、その場合は特に飲酒の時間を短くしなければいけません。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・焼酎は麦や芋などを蒸留してつくるため、糖分がほとんど入っておらず、虫歯のリスクが低い
・麦焼酎はpH値が限りなく中性に近いため、歯のエナメル質を溶かす心配も少ない
・焼酎の虫歯リスクをさらに減らすには、ストレートや水割り、ロックで飲むのがおすすめ
・長時間ダラダラと飲まないように注意が必要
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。