東京にきています。
勉強です。。。。
今日は経営系です。
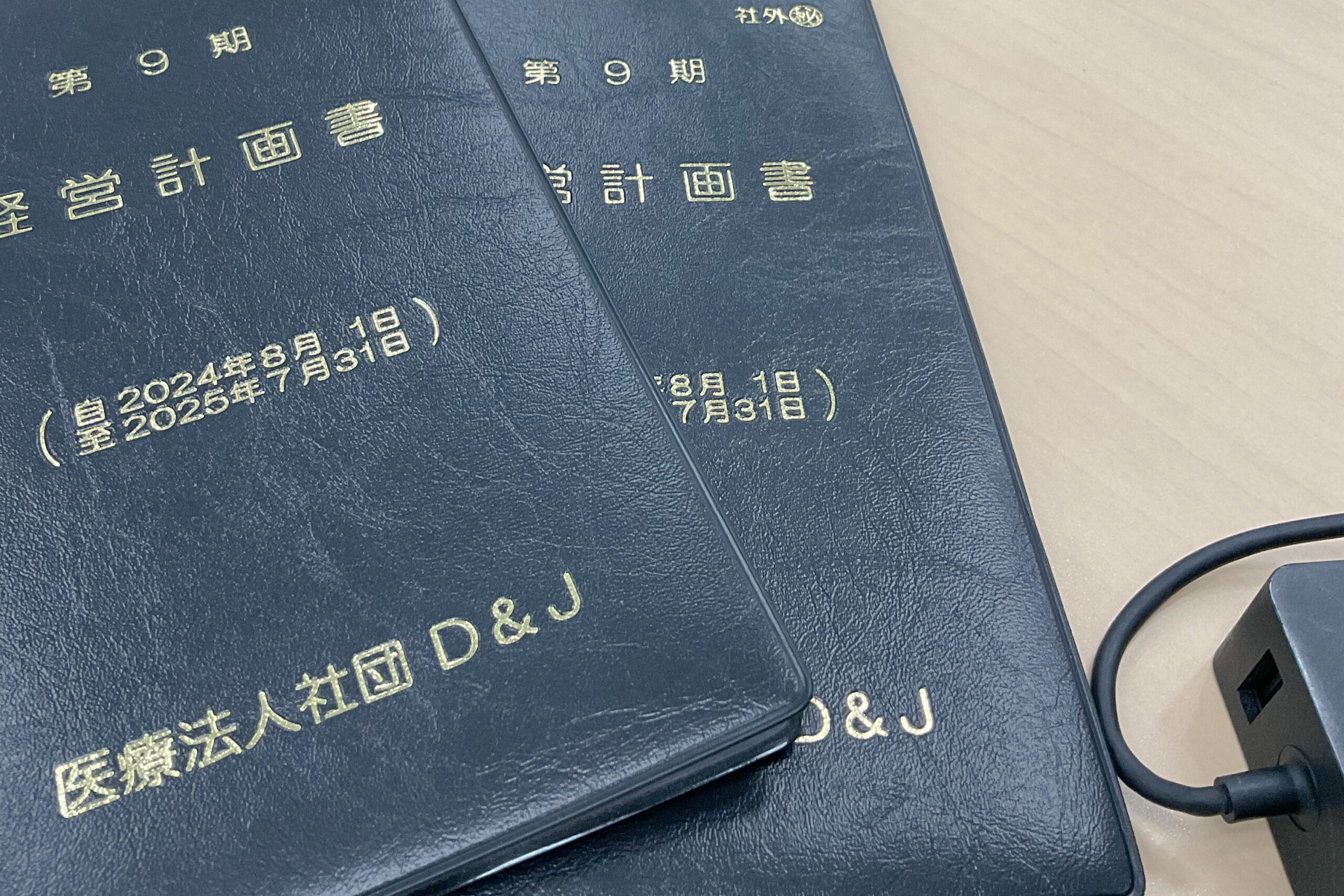
なんとしても、
年間休日を増やしたい
給与を上げ続けたい
ずっと働ける環境にしたい
楽しい職場にしたい
だから勉強する。
「社長の無知は犯罪」
その通り。。。。。。
だから頑張る💪
東京にきています。
勉強です。。。。
今日は経営系です。
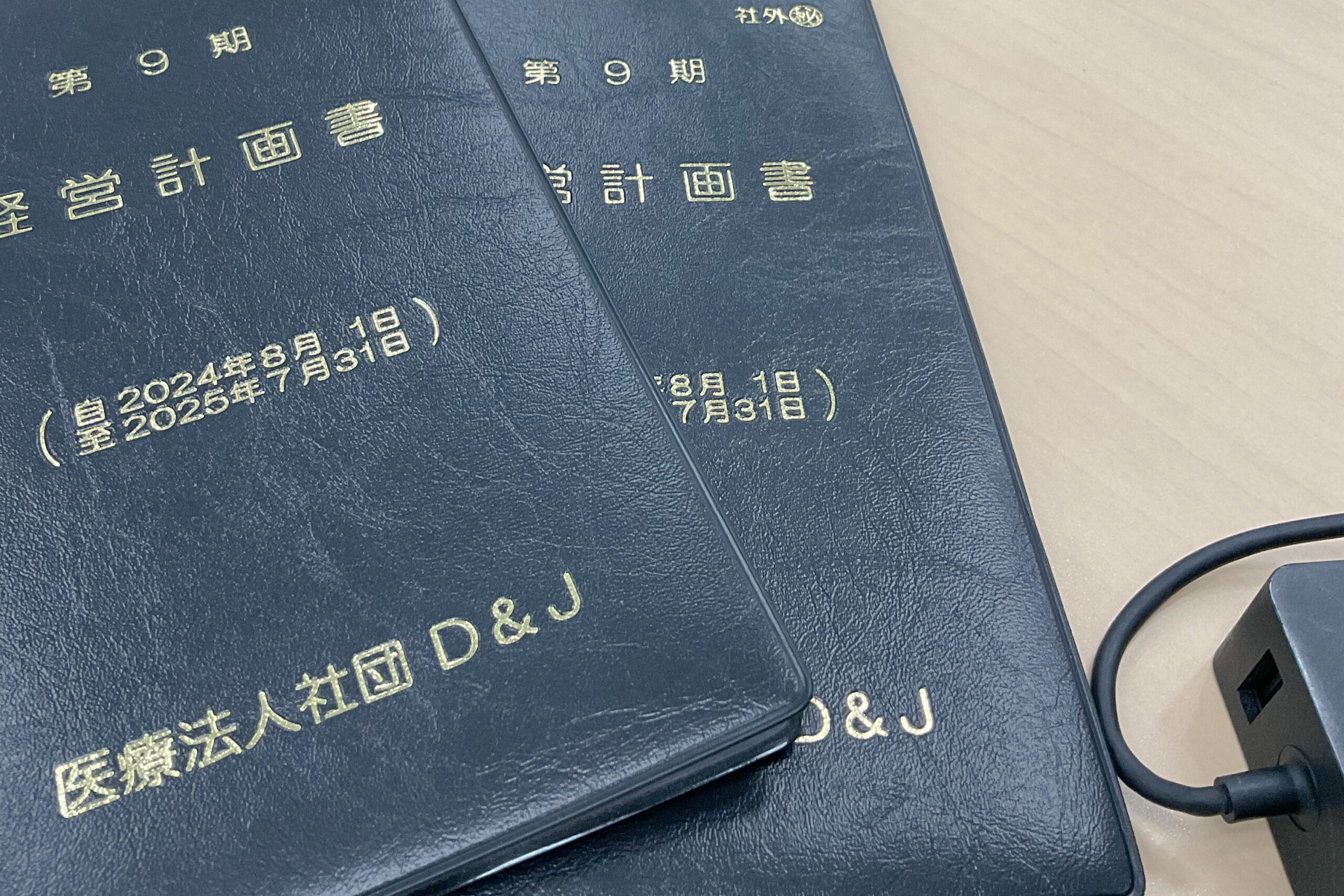
なんとしても、
年間休日を増やしたい
給与を上げ続けたい
ずっと働ける環境にしたい
楽しい職場にしたい
だから勉強する。
「社長の無知は犯罪」
その通り。。。。。。
だから頑張る💪
歯周病は自覚症状があまりなく、目立った症状があらわれたときには、かなり進行しています。
実は、歯周病にはいくつかの段階があるのです。
歯周病を発症したのにも関わらず治療しなかった場合、どのように進行していくのでしょうか?
歯周病の進行状況を段階と症状ごとに解説します。
歯周病は、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の溝に歯周病の原因となる菌が侵入し、さまざまな症状を引き起こす病気です。
歯周病の進行過程は、以下のとおりです。
歯肉炎
軽度歯周炎
中度歯周炎
重度歯周炎
それぞれどのような状態なのか解説します。
歯周病の初期段階で、歯茎が赤く腫れてブラッシングをしたときに出血することがあります。
歯と歯茎の溝の深さは2〜3mmで、まだ歯がグラグラすることはありません。
この段階で、歯周病を発症しているとは気づきにくいでしょう。
歯肉炎のときに適切な処置を行わなければ、進行して軽度歯周炎になります。
歯茎の炎症がひどくなり、歯と歯茎の溝の深さは3〜5mmになります。
この段階で歯を支えている歯槽骨が破壊され、歯茎が下がり始めますが、まだ歯周病だと気づかない人も多いでしょう。
軽度歯周炎だと気づかずに放置すると、中度歯周炎へと進行してしまいます。
歯槽骨が半分ほど破壊され、歯と歯茎の溝の深さは4〜7mmになり、歯がぐらついてきます。
また、歯茎から膿が出てきて口臭がひどくなるため、この段階で歯周病だと自覚する人が多いです。
気になる症状があるにもかかわらず、歯科医院を受診しなければ重度歯周炎へと進行します。
歯と歯茎の溝の深さは6mm以上になり、歯槽骨が半分以上破壊されて歯のぐらつきは大きくなるでしょう。
食事にも支障をきたし、この段階でやっと歯科医院を受診する人もいます。
最終的には、歯が抜け落ちてしまうでしょう。
歯周病を防ぐには、歯垢や歯石の除去が大切です。
定期的に歯科医院を受診し、歯の歯垢や歯石を除去してもらいましょう。
また、定期的に受診することで口内の状態を確認してもらうと、歯周病の早期発見につながります。
歯周病とは、歯周ポケットに歯周病の原因となる菌が侵入し、さまざまな症状を引き起こす病気です。
進行過程は、4つに分けられ初期の歯肉炎の状態では気づかない人が多いでしょう。
ただし、この段階で歯科医院を受診して適切な治療を行えば、完治する可能性があります。
中度歯周炎で気づく人もいますが、歯がグラグラして食事に支障をきたすようになる重度歯周炎の状態になってから歯科医院を受診する人も少なくありません。
歯周病を予防するためには毎日の歯磨きが重要ですが、食べ物にも気をつける必要があります。
歯周病を予防するためには、何を食べるのがいいのでしょうか?
また、飲み物は何が歯周病予防に効果があるのでしょうか?
本記事では歯周病を予防する食べ物や飲み物について解説します。
日々の食事に取り入れてみてください。
歯周病を予防するためには、主に以下のものを食べることが大切です。
食物繊維が豊富な食べ物
カルシウムを含む食べ物
ビタミンが豊富な食べ物
質のよい脂を含む食べ物
具体的に何を食べたらいいのか解説します。
食物繊維が豊富な食べ物はよく噛んで食べなければなりません。
よく噛んで唾液を分泌することで、歯周病の予防に効果があります。
食物繊維が豊富な食べ物は、主に以下のとおりです。
にんじん
ごぼう
大根
きのこ類
海藻類
豆類 など
歯を支えている骨を丈夫にすることも、歯周病の予防につながります。
カルシウムは骨を丈夫にする成分です。
カルシウムを含む食べ物は、以下のとおりです。
牛乳
チーズ
ヨーグルト
豆腐
小魚
切り干し大根 など
歯周病を予防するためには、歯周病の原因となる菌に感染しないように免疫力を高める必要があります。
ビタミン類は免疫力アップに効果があります。
ビタミンが豊富な食べ物は、以下のとおりです。
にんじん
ほうれん草
カボチャ
ブロッコリー
キウイフルーツ
アセロラ
レモン など
質のよい脂を含む食べ物を摂取することも、歯周病の予防には大切です。
質のよい脂を含む食べ物や食品は次のとおりです。
ナッツ類
ごま
アマユ油
オリーブオイル など
歯周病を予防する飲み物は、以下のものが挙げられます。
緑茶
ポリフェノールの一種であるカテキンには、抗菌作用や抗酸化作用があります。
また、カテキンには歯垢の付着を抑制する働きや歯垢を合成する酵素の働きを阻害する効果もあるのです。
烏龍茶
烏龍茶に含まれているポリフェノールは、カテキンよりも抗菌作用が高いのが特徴です。
また、カテキンと同様に歯垢の付着を抑制する働きがあります。
麦茶
ミネラルが含まれていて、歯周病の予防に効果があるビタミンCの吸収をサポートします。
特に喫煙習慣がある人はビタミンCの吸収率が低下するため、麦茶を飲んでビタミンCを摂取してください。
歯周病は毎日の歯磨きが重要ですが、食べ物や飲み物にも気をつける必要があります。
食べ物であれば、食物繊維やカルシムが豊富な食べ物、ビタミンや質のよい脂を含むものがいいでしょう。
飲み物は、緑茶や烏龍茶、麦茶がおすすめです。
前述した食べ物が苦手な人もいるかもしれません。
今回紹介したのはあくまでも一例であるため、自分が食べられるものからうまく摂取して、美味しく予防しましょう。
矯正治療を受けたいとは思っても、痛みがあると聞いて迷っている人もいるでしょう。
矯正治療は、本当に痛いのか、痛みがあるとしたらどのくらい続くのか、気になるところです。
今回は、矯正治療で生じる痛みの度合いと、痛みが続く期間について解説します。
矯正治療を受けようか迷われている人はぜひ参考にしてください。
矯正治療の痛みの感じ方には個人差があり、中には全く感じない人もいます。
矯正治療を受けたからといって、必ずしも全員が痛みを感じるわけではありません。
痛みといっても、虫歯のような鋭い痛みではなく、鈍い痛みを感じる人が多いようです。
矯正治療の痛みは、若い人の方が弱く感じやすいようです。
また、神経質な方や心配性な方は強く痛みを感じてしまう傾向があります。
矯正治療の種類によっても痛みの大きさは異なり、特に痛みを感じやすいのがワイヤー矯正、痛みを感じにくいのがマウスピース矯正です。
矯正治療で我慢できないほど痛みを感じる場合には、歯科医師に相談しましょう。
ワイヤー矯正のケースでは締め付けを調整し、強い痛みが出にくいようにしてもらえる場合があります。
痛みは矯正治療が完了するまで、ずっと続くというわけではありません。
矯正装置を装着してから3~6時間ほど過ぎた後に、痛みが出始めます。
徐々に痛みが強くなり、2~3日ほどでピークを迎えますが、約1週間で気にならなくなるでしょう。
矯正治療の痛みは、歯が動くことで発生する痛みです。
この痛みが無ければ、歯は適正な位置に向かって動きません。
痛いと感じるのは矯正治療が順調に進んでいる証拠です。
ある程度は仕方がないと受け止めましょう。
矯正治療では、歯が動く以外に痛みが出るケースがあります。
ワイヤー矯正で矯正治療をしているケースでは、口腔内の粘膜にワイヤーが当たって傷つき、痛みを感じることがあるのです。
また、ワイヤー矯正では食べ物を噛んだときの刺激で痛みが発生するケースもあります。
特にワイヤーを調整した後や矯正治療開始直後、新しいマウスピースに交換したあとは、痛みやすくなるでしょう。
痛いときは、硬いものを避けて柔らかいものを食べましょう。
矯正治療には痛みがつきものであるため、受けようか迷う人もいるでしょう。
痛みの感じ方は個人差があるため、必ずしも強い痛みを感じるわけではありません。
また、治療が完了するまでずっと痛みがあるわけではなく、矯正装置を装着した最初の1週間前後だけ痛みがあります。
矯正治療で我慢できないほど痛いときは、歯科医師に相談しましょう。
大人になってから矯正治療を行う際に気になるのが、どのくらいの治療期間がかかるのかという点ではないでしょうか。
また、矯正治療が計画通りに行われ、治療期間が長引かないようにするにはどうしたらいいのか気になる人もいるかもしれません。
大人の矯正治療の治療期間と治療期間を長引かせない方法について解説します。
矯正の治療方法別の治療期間の目安は、だいたい下表のとおりです。
| 表側矯正(ワイヤー矯正) | 2年~3年程度 |
| 裏側矯正(ワイヤー矯正) | 2年~3年程度 |
| 全体マウスピース矯正 | 1年半~2年半程度 |
| 部分矯正 | 数ヶ月~1年半程度 |
歯の裏側にワイヤーを取り付ける裏側矯正と、表側にワイヤーを取り付ける表側矯正がありますが、どちらも治療期間にあまり差はありません。
矯正装置を目立たせたくない人は、裏側矯正がおすすめです。
マウスピース矯正は、取り外しが可能な矯正装置で金属アレルギーの人でも利用できます。
取り外しが可能だからといって、外している時間が長いと矯正治療が進まず矯正期間が長引く可能性があります。
治療期間の目安にかなりの幅があるのは、歯並びの状態や矯正を始める年齢によって異なるためです。
歯科医院で検査を受けると、正確な治療期間を知ることができるでしょう。
前述した矯正期間の治療期間の目安は、治療計画が予定通りに進んだ場合の期間です。
矯正期間を長引かせず計画通りに終わらせる方法は、次のとおりです。
歯科医院を慎重に選ぶ
歯科医師の指示を守る
歯磨きを丁寧に行う
矯正治療を長引かせないためには、経験豊富で専門性の高い歯科医師がいる歯科医院を選ぶことが大切です。
ただし、矯正期間中定期的に通院するため、通いやすい立地にある歯科医院を選ぶことも重要になります。
マウスピース矯正であれば装着時間、ワイヤー矯正であれば月に一度通院するなど歯科医師からの指示を守らなければ、治療期間が長引いてしまいます。
矯正治療をしている間は、歯磨きを丁寧に行い、プラークなどを取り除きましょう。
虫歯や歯周病を発症すると、矯正治療を一時中断して虫歯や歯周病の治療を行う必要があるため、矯正治療の治療期間が長引いてしまいます。
大人が矯正治療を行うと、治療期間の目安は1年半から3年程度、部分矯正でも数ヶ月から1年半程度かかります。
期間の目安にかなりの幅があるのは、歯並びの状態や矯正を始める年齢によって異なるためです。
歯科医院で検査を受けると、正確な治療期間を知ることができるでしょう。
治療期間を長引かせず治療計画通りに終わらせたいのであれば、経験豊富な医師のいる病院を選び、医師からの指示を守り歯磨きを丁寧に行いましょう。
口腔内のトラブルの一つに、歯槽膿漏という病気があります。
歯周病の中でも最も重い症状で、歯を失う原因にもなりえる病気です。
何が原因で、歯槽膿漏になるのでしょうか?
また、予防する方法はないのでしょうか?
歯槽膿漏の主な原因と予防する方法について解説します。
歯槽膿漏の原因になるのは、歯に付着しているプラークです。
プラークの中には、歯槽膿漏の原因となる菌をはじめとしたさまざまな細菌が棲みついています。
歯磨きが不十分な場合、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間などにプラークが溜まり、歯槽膿漏の原因となる菌が増殖してしまうのです。
歯槽膿漏は急になるわけではありません。
歯肉炎から軽度歯周病へ進行し、さらに中度歯周病から重度歯周病へと進行します。
歯槽膿漏は、独自の病気ではなく重度歯周病になった状態のことを指しているのです。
歯周病は、歯肉炎の段階では気づかない人も多く、かなり進行しなければ気づきにくい病気です。
歯槽膿漏は、口臭がひどくなるなどのわかりやすい症状が現れますが、その時にはもう手遅れのケースが多いのです。
歯槽膿漏を予防する方法は、次のとおりです。
1. 毎日の歯磨き
2. 歯石の除去
3. 生活習慣を見直す
それぞれについて詳しく解説します。
前述したとおり、歯槽膿漏の原因は歯に付着しているプラークです。
丁寧に歯磨きをしてプラークを口内に溜めないことが、予防するうえで重要になります。
歯磨きは自己流になりやすいため、定期的に歯科医院でブラッシング指導を受けて正しい歯磨きを身につけましょう。
デンタルフロスを併用するのもおすすめです。
自宅で丁寧に歯磨きをしたうえでデンタルフロスを併用しても、プラークを100%除去することはできません。
除去できなかったプラークは少しずつ口内で蓄積し、歯石に変わります。
歯石は歯磨きでは除去できないため、歯科医院で除去してもらいましょう。
乱れた食生活を送っているとプラークが溜まりやすくなります。
正しい食生活を送るように心がけてください。
喫煙習慣がある人は、歯茎の血流を悪くなり歯槽膿漏の原因となる菌が繁殖しやすくなります。
タバコは、できれば禁煙するか極力控えてください。
歯槽膿漏の原因は、歯に付着しているプラークの中に棲みついている菌です。
歯磨きがしっかりできていないと、歯周ポケットにプラークが溜まります。
その結果、歯槽膿漏の原因となる菌が増殖してしまうのです。
歯槽膿漏を予防するためには、丁寧に歯磨きをすることが大切ですが正しい歯磨きを身につけるためにも歯科医院でブラッシング指導を受けてください。
ただし、歯磨きをしても全てのプラークは除去できないため、定期的に歯科医院に通い、除去してもらいましょう。
口内に何らかのトラブルが発生していることを自覚していても、なんとなく歯科医院へ行くのが面倒だと思う人もいるでしょう。
しかし、歯科医院へ行くことを考えるだけで動悸がしたり涙が出てきたりする人は、もしかすると歯科恐怖症かもしれません。
歯科恐怖症について解説します。
歯科恐怖症とは、過去に歯科治療で受けた痛みなどが原因で心に深い傷を負ってしまい、再び歯科医院へ行こうとすると強い恐怖や不安を感じ、身体に異変が起こることをいいます。
歯科恐怖症の主な症状は、以下のとおりです。
歯科治療を考えるだけで動悸やめまいがする
大量の汗が出でたり過呼吸が起きたりする
歯を削るための機械の音で身体が硬直する
治療時に吐き気がする
診療台に座れない、もしくは一定時間以上座ることができない
意識を失ってしまう
歯科恐怖症は心の病気の1つとされていますが、「歯科医院」という特定の場所が対象となっているのが特徴です。
全国で約500万人、割合でいうと20人に1人の人が同様の悩みを抱えているとされています。
歯科恐怖症を乗り越えるためには、まず何が怖いのか理解することが大切です。
自分一人で克服するのは難しいため、カウンセラーの助けを借りることをおすすめします。
次に、歯科治療に対する心の傷に寄り添ってくれる歯科医院を探します。
口コミやホームページを見たり、周囲から情報を集めたりするとよいでしょう。
一人で歯科医院へ行くのが難しければ、友人や家族に付き添いを頼んでください。
歯科医院へ行くことができたら、即座に治療を受けるのではなく、歯のクリーニングなどから始めて少しずつ歯科医院に慣れましょう。
治療に進む前に、歯科医師に治療への不安や恐怖心を打ち明け、理解してもらえると歯科恐怖症を乗り越えられる可能性が高くなります。
実際の治療に進み、どうしても恐怖心や不安が取り除くことができなければ、「笑気吸入鎮静法」や「静脈内鎮静法」を使って治療を受けましょう。
歯科恐怖症とは、歯科治療を考えるだけで動悸やめまいがする心の病気の1つです。
全国で約500万人、20人に1人の人が同様の悩みを抱えているとされ、決して珍しい病気ではありません。
乗り越えるためには、歯科治療の何が怖いのか理解することが大切です。
自分だけでは難しい場合には、カウンセラーの助けを借りることもおすすめです。
どうしても治療を受けられない場合は、静脈内鎮静法などを使って治療を受けましょう。
インプラント治療は、さまざまな理由で永久歯を喪失した人に人気の治療方法です。
インプラント治療には多くのメリットがありますが、治療を受けてからどのくらい使うことができるのか、知らない人も多いでしょう。
インプラントの寿命は、何年程度なのでしょうか?
また、長く使用するためにはどうしたらいいのか解説しまsう。
インプラントは、一般的に治療を受けてから10年から15年程度使用できるとされています。
つまり、寿命の平均は長くても15年程度ということです。
ただし、寿命が経過したからといって壊れたりするということはほとんどありません。
寿命である15年が経過しても、90%以上のインプラントは残っているのです。
インプラントの寿命は、日々の手入れによって大きく変動します。
人工歯だから手入れをしなくてもいいと考えていると、寿命が短くなってしまうのです。
インプラントを長く使用したいのであれば、日々の手入れをしっかり行うことが大切です。
インプラントの寿命を延ばすためには、次のことを心がけましょう。
定期メンテナンスを受ける
禁煙する
食いしばりを軽減する
インプラントを何もせずに放置していると、歯周病の一種である「インプラント歯周炎」を発症するリスクが高まります。
歯科医院で定期メンテナンスを受けて、インプラント歯周炎を防ぎましょう。
喫煙習慣がある方は、インプラント治療を受けたことをきっかけに禁煙することをおすすめします。
歯茎の血流が悪くなってしまい、インプラントの寿命が短くなる傾向にあるためです。
インプラントは人工歯であることから、衝撃にあまり強くありません。
食いしばりをすることで、人工歯に負担がかかり破損したり、寿命に悪影響を与えたりする可能性があります。
食いしばりをする方は、マウスピースなどを使用してかかる力を軽減しましょう。
インプラントの平均寿命は10年から15年ほどですが、寿命を経過したからといって破損することはありません。
むしろ、寿命を経過した後も残っていることが多いのです。
ただし、日々の手入れを怠ると寿命が短くなる可能性もあります。
寿命を延ばすためには、定期メンテナンスを受けましょう。
また、喫煙習慣のある方はこの機会に禁煙してください。
食いしばりをする方は、マウスピースなどを使用して食いしばりを軽減しましょう。

今日新潟に帰ります〜。
朝から晩までず〜〜〜っとPC を見ています。
頭から煙が出そう。。。。
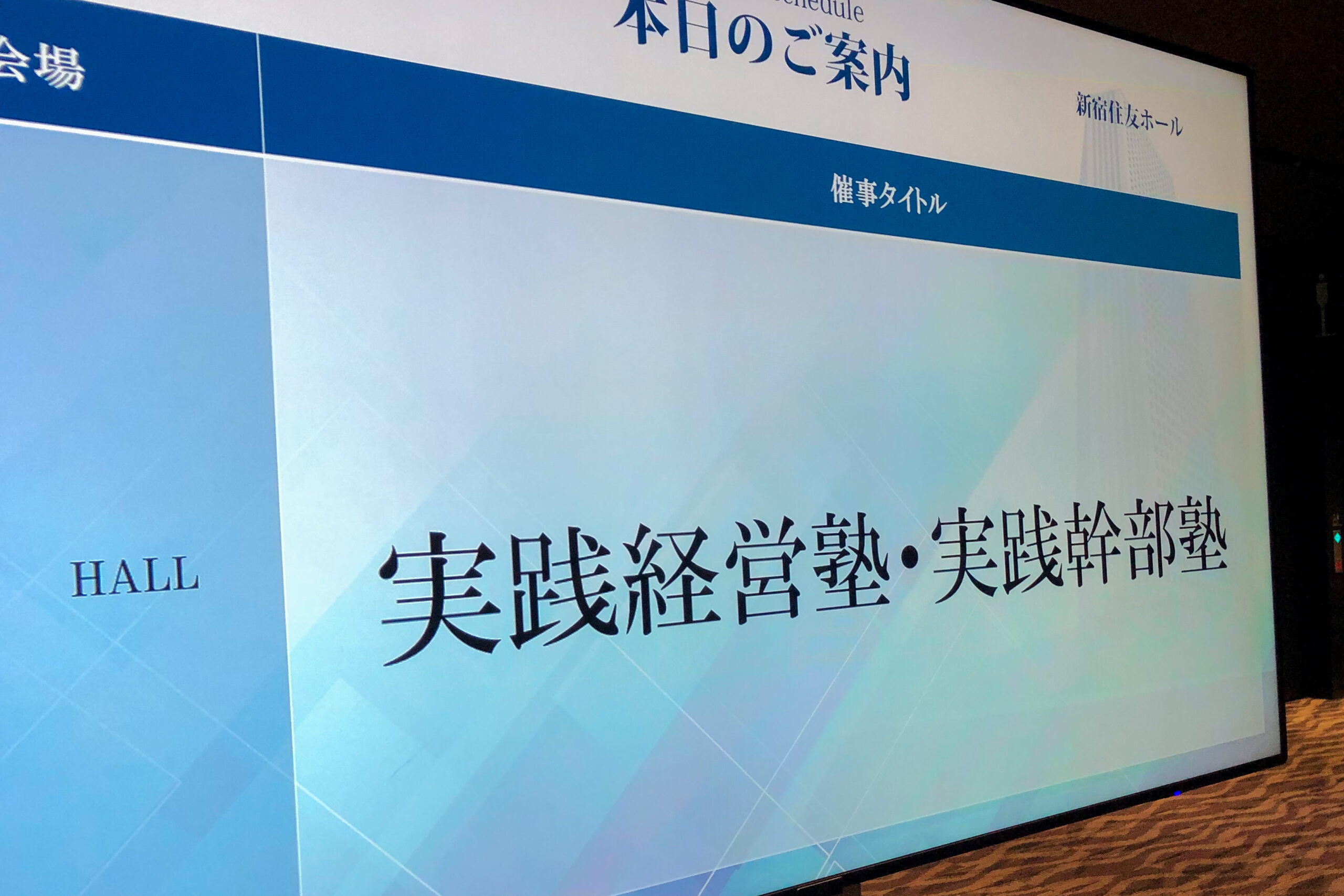
頭を使って使いすぎて。。。。キャパオーバーです。。。
で、思いました。
頭を普段使っていないのだ。
無理をしていないのだ。。。。
毎日、限界まで頭を動かそう。
できることをやり続けよう。
患者さんとスタッフのみんなが幸せになるように、もっとできることをやろう!
涼しくなった今日この頃。。。
みなさまいかがお過ごしでしょうか?

私は、朝さんぽ。。。
涼しくて気持ちがいい〜。

今日は東京です。
経営の研鑽です。
みんな働きやすく、楽しい会社にしたいと切に思っています。
がんばります。
成果は出るはず。。。