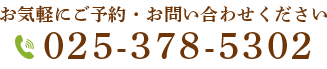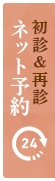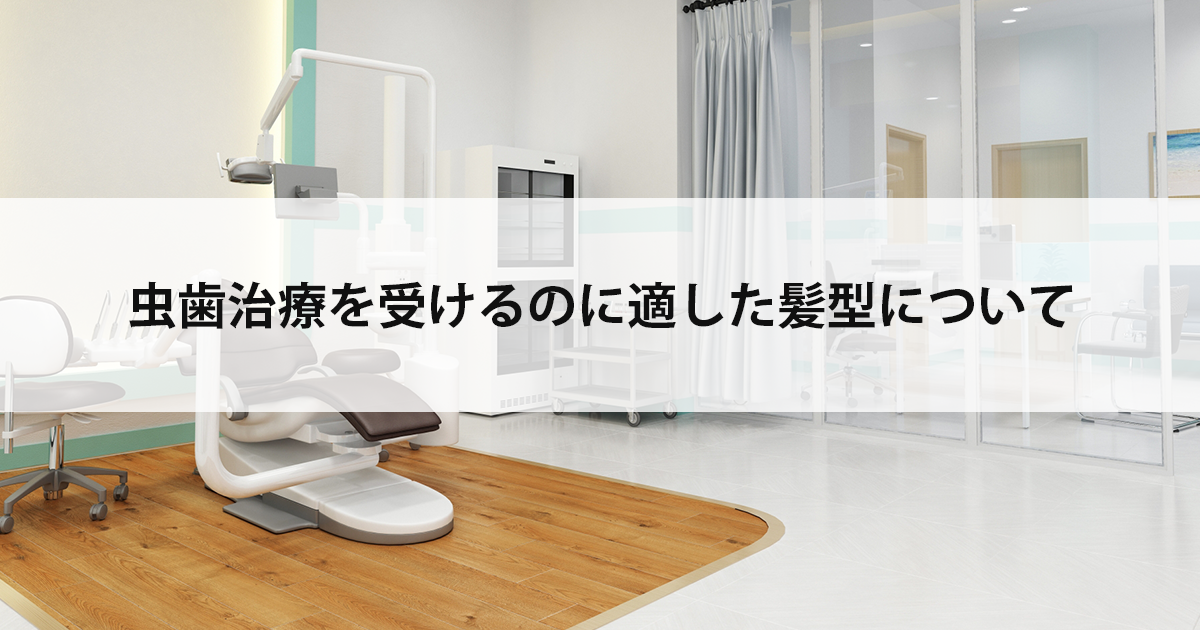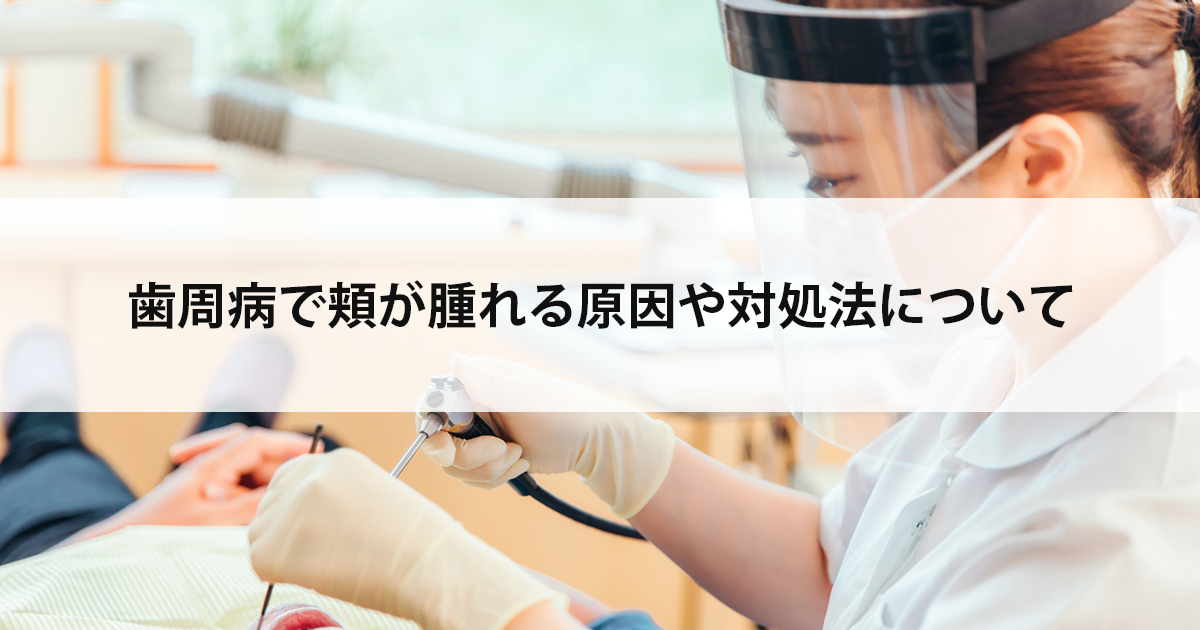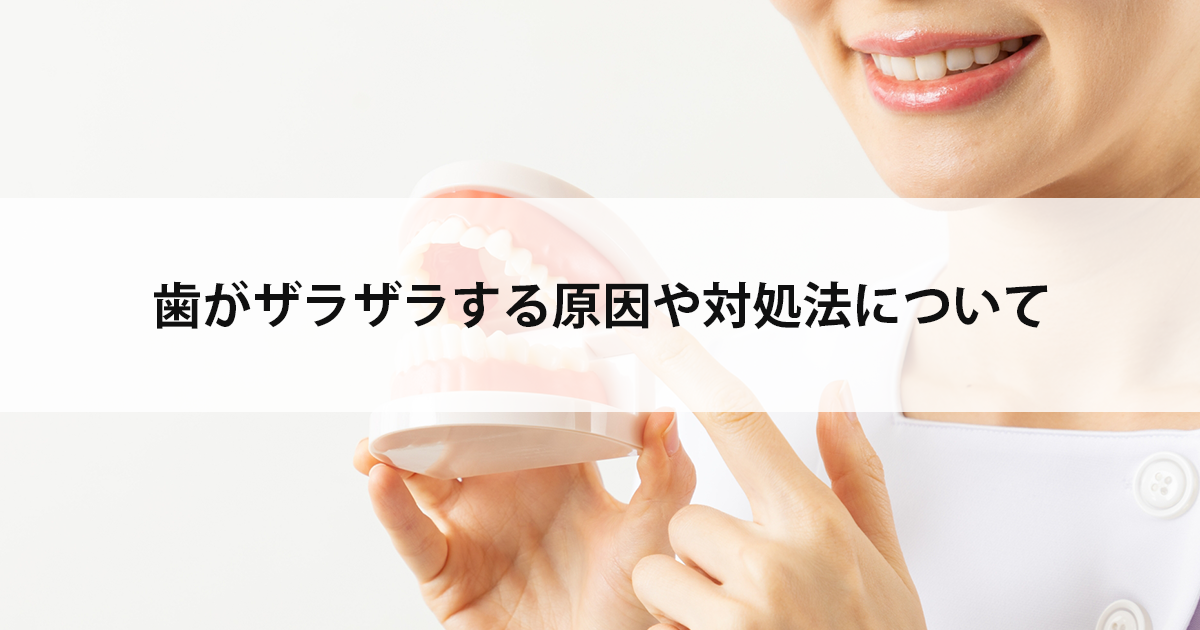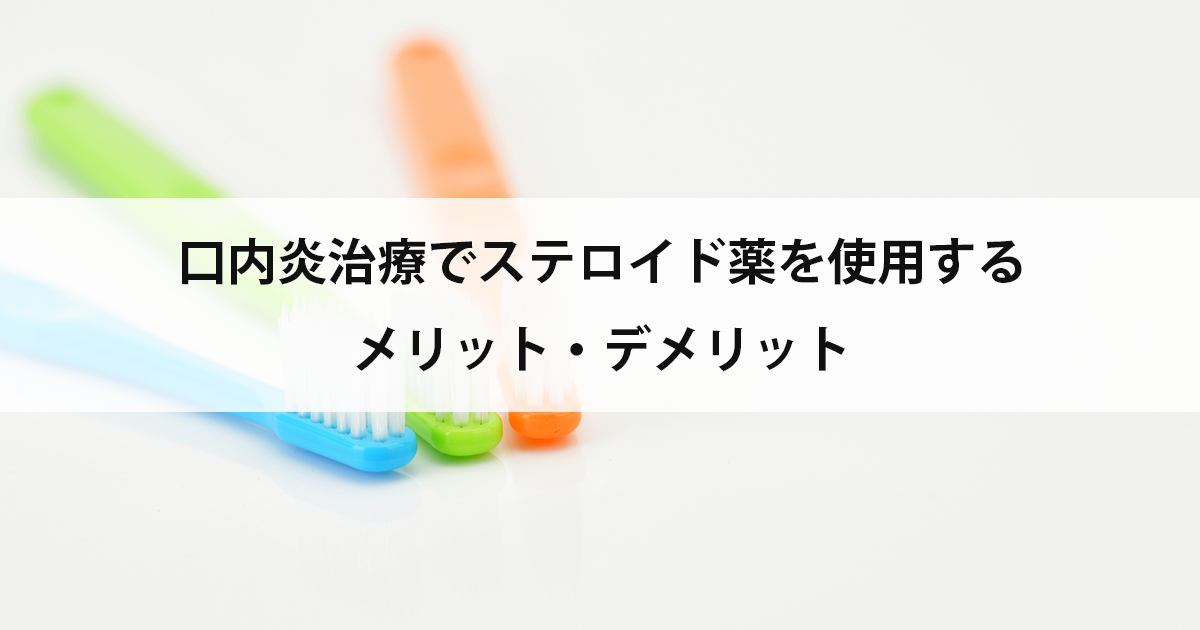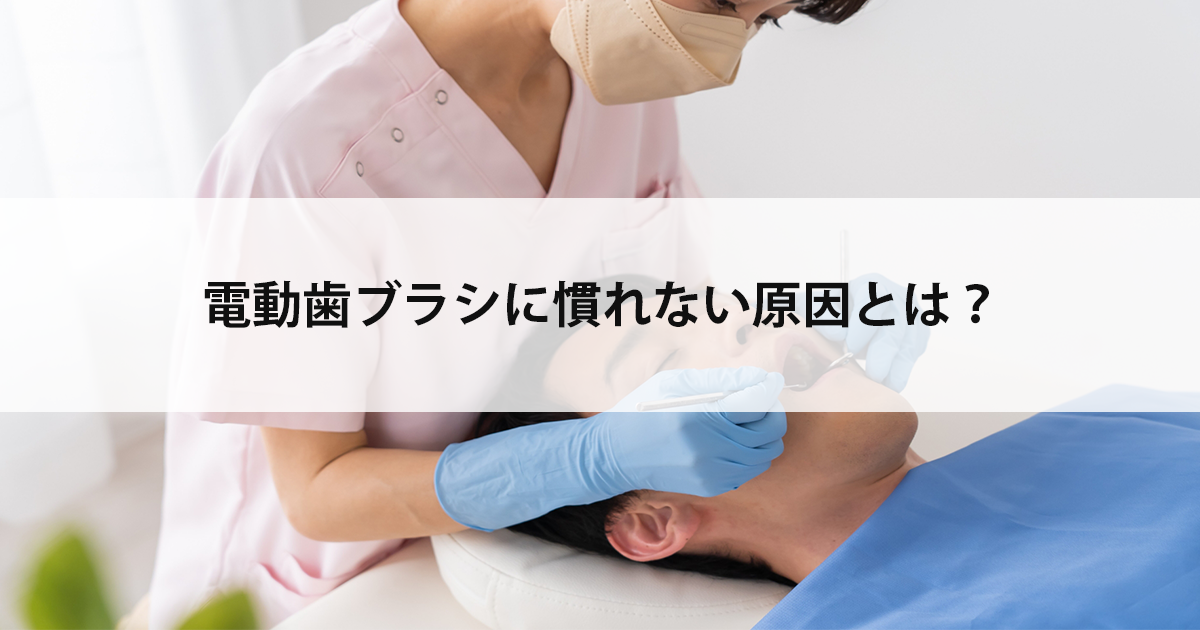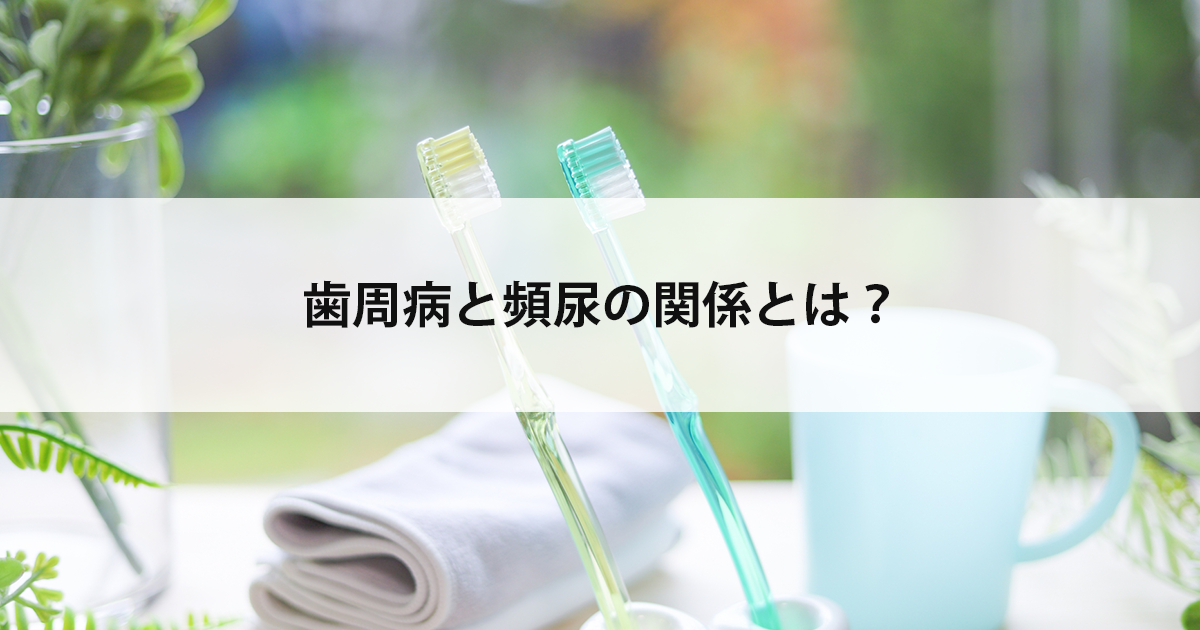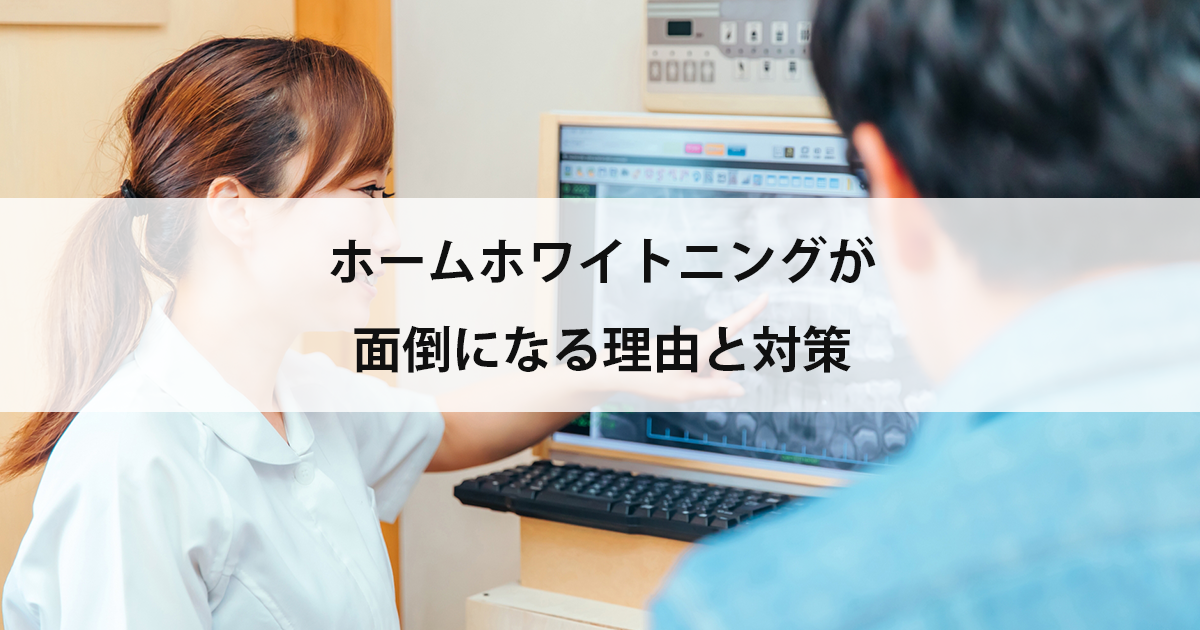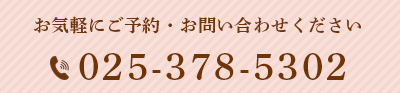虫歯治療を受ける際は、治療がスムーズにいくように、患者さんもある程度準備することが望ましいです。
例えば、事前にブラッシングをして口内をキレイにしておいたり、虫歯治療がしやすい服装や髪型にしたりすることが挙げられます。
今回は、虫歯治療を受けるのに適した髪型について解説します。
虫歯治療を受けるのに適した髪型
男性は短髪のケースも多いため、そこまで髪型について気にする必要はないと言えます。
一方、女性は髪が長いことも多いため、結ぶときはなるべくサイドで結ぶようにしましょう。
サイドの低い位置でまとめれば、診察台で仰向けになっても髪が邪魔になりません。
またポニーテールの場合でも、結び目を首の付け根当たりの低い位置にすれば、診察台との干渉を最小限に抑えられます。
虫歯治療で避けるべき髪型
虫歯治療で避けるべき髪型としては、まず後頭部に大きな結び目をつくる髪型が挙げられます。
こちらは仰向けになったとき、結び目やヘアアクセサリーが診察台に当たり、頭が不安定になります。
また高い位置のポニーテールも、頭が左右に揺れやすくなり、精密な治療が必要な虫歯治療では危険を伴う場合があります。
さらに、ヘアピンを使用して前髪を留める場合は、金属製のものを避けるようにしましょう。
金属はレントゲンの撮影時に影が映り込む可能性があるため、外す手間が生じます。
その他の避けるべき服装やファッションアイテム
虫歯治療を受けるときは、必ず帽子を取らなければいけません。
帽子は頭が安定しにくくなるだけでなく、つばや大きさによっては、歯科医師や歯科衛生士が治療部位を見るのを妨げる可能性があります。
また虫歯治療時には、簡単に着脱できないパーカーも着用しないことをおすすめします。
パーカーにはフードが付いているため、仰向けになったときに後頭部が不安定になりやすいです。
さらに女性の場合、スカートではなくパンツスタイルで来院することも大切です。
スカートの場合、診察台でリクライニングをしたり体勢を変えたりする際、足元が大きく開いたり捲れ上がったりして、羞恥心や不快感につながることがあります。
タイトスカートの場合は、動きにくかったり座る際に不便さを感じたりする可能性も高いです。
この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・髪が長い場合、頭の低い位置でまとめることで、スムーズに虫歯治療を受けやすくなる
・高い位置のポニーテールなどは頭が左右に揺れやすくなり、虫歯治療では危険を伴う
・虫歯治療の際は帽子を脱ぎ、フード付きのパーカーもなるべく避ける
・女性はスカートではなく、パンツスタイルで来院すべき
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。