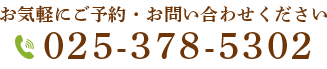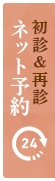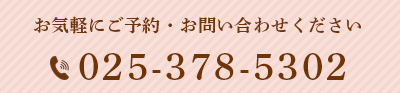歯科クリニックで行われる根管治療は、重度の虫歯などで傷んだ歯髄を除去し、根管を消毒した後、再感染を防ぐために詰め物をする治療です。
では、こちらの治療には、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
また、治療中は何回くらい通院すれば良いのでしょうか?
今回はこれらの点について解説します。
〇根管治療の費用相場について
根管治療の費用相場は、保険診療なのか自由診療なのかによって大きく変わってきます。
保険診療で行う根管治療では、レントゲン撮影を行った後、虫歯部分を取り除き、ファイルと呼ばれる細い棒状の器具で根管内の汚れをかき出します。
しかし、ファイルには硬くパワーがある一方で、しなやかさに欠けるため、曲がった形状の根管などは先端まで届きにくく、細菌の取り残しを招くことがあります。
こちらにかかる費用の相場は、3割負担の方で5,000~8,000円程度です。
一方、自由診療の根管治療は、治療を成功に導くために、保険診療では使用できないCT、マイクロスコープ、ラバーダムなどを使用します。
そのため、保険診療に比べて成功率は高いです。
ただし、その分金額は高くなり、歯科クリニックによって変動はありますが、相場は50,000~20万円程度になります。
〇根管治療の治療回数について
根管治療の治療回数は、虫歯の進行度や根管の形、根管治療が必要な歯の本数によって変わってきます。
虫歯になっている歯を削り、根管内の清掃や消毒が終わるまでの治療回数は、前歯で2~3回、奥歯で3~4回が目安です。
ただし、痛みが長引いている場合は、感染を治療し、炎症が治まるのを待たなくてはいけないため、さらに治療回数が増える可能性があります。
また、根管の形状が複雑である場合は、清掃や消毒に時間がかかるため、通院の回数も多くなる傾向にあります。
さらに、根管治療は、清掃や消毒をして完了するわけではありません。
これらの処置が完了したら、被せ物を装着する必要があり、こちらの作製や装着にかかる治療回数は、平均で3回です。
つまり、どれだけスムーズに根管治療が完了したとしても、5~6回程度は歯科クリニックに通わなければいけないということです。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・根管治療には保険診療と自由診療があり、自由診療の方が成功率は高い
・保険診療の根管治療にかかる費用の相場は、3割負担の方で5,000~8,000円程度
・自由診療の根管治療の費用相場は、50,000円~20万円程度
・根管治療はスムーズに完了したとしても、最低5~6回は通院する必要がある
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。