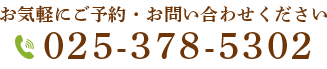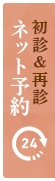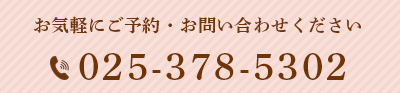成人してからでも、ケガや虫歯、歯周病などの理由により、歯が欠損することはあります。
また、このような場合に「1本欠損したくらいなら大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、実際は放置してはいけません。
ここからは、歯が欠損した状態を放置するデメリットについて解説します。
〇噛み合っていた歯が伸びる
歯が欠損した状態を放置すると、失った歯と過去に噛み合っていた歯が伸びてくることがあります。
具体的には、噛み合う歯がない上の歯は下方向に、下の歯は上方向に伸びることが考えられます。
こちらは歯の挺出と呼ばれる現象であり、一度発症すると噛み合わせのバランスが悪化し、一部の歯にだけ大きな負担がかかります。
また、大きな負担がかかり続けた歯は、他の歯と比べて摩耗が激しくなったり、場合によっては割れたりしてしまうおそれがあります。
〇老け顔に見える
老け顔に見えることも、歯が欠損した状態を放置するデメリットの1つです。
たとえ1本であっても、歯が欠損すると全体の噛む力は低下します。
噛む力が弱くなると顔の筋力も低下し、シワやたるみが増え、老け顔に見えてしまうという仕組みです。
また、歯が欠損した状態でいると、当然噛み合わせは悪いままのため、無意識に噛むことを避けるようになります。
このような行動が、表情筋の衰えにつながることも考えられます。
〇その他のデメリットは?
歯が欠損した状態を放置するその他のデメリットとしては、消化器官の負担が大きくなることも挙げられます。
1本でも歯を失うと、これまでと同じようにものを噛むことは難しくなり、硬いものもしっかり砕くことができず、飲み込むケースが多くなります。
その結果、消化器官に負担がかかり、胃もたれなどの症状につながる可能性があります。
また、発音が悪くなることも、歯が欠損した状態を放置するデメリットです。
これまでと同じように発音しているつもりでも、歯がない部分から空気が漏れると、発音が不明瞭になり、会話が成立しにくくなるおそれがあります。
そして、会話がしにくいことにより、コミュニケーションを取るのが億劫になったり、精神的にふさぎ込んでしまったりすることも考えられます。
〇この記事のおさらい
今回の記事のポイントは以下になります。
・歯が欠損した状態を放置すると、失った歯と過去に噛み合っていた歯が伸びることがある
・歯を失い、噛む力が弱くなるとシワやたるみが増え、老け顔に見える
・歯がない状態が続くと、胃などの消化器官に負担がかかりやすくなる
・歯が欠損した部分から空気が漏れると、発音が悪化する
以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!
新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!
スタッフ一同、心よりお待ちしております。